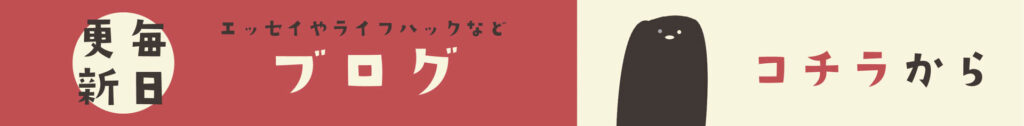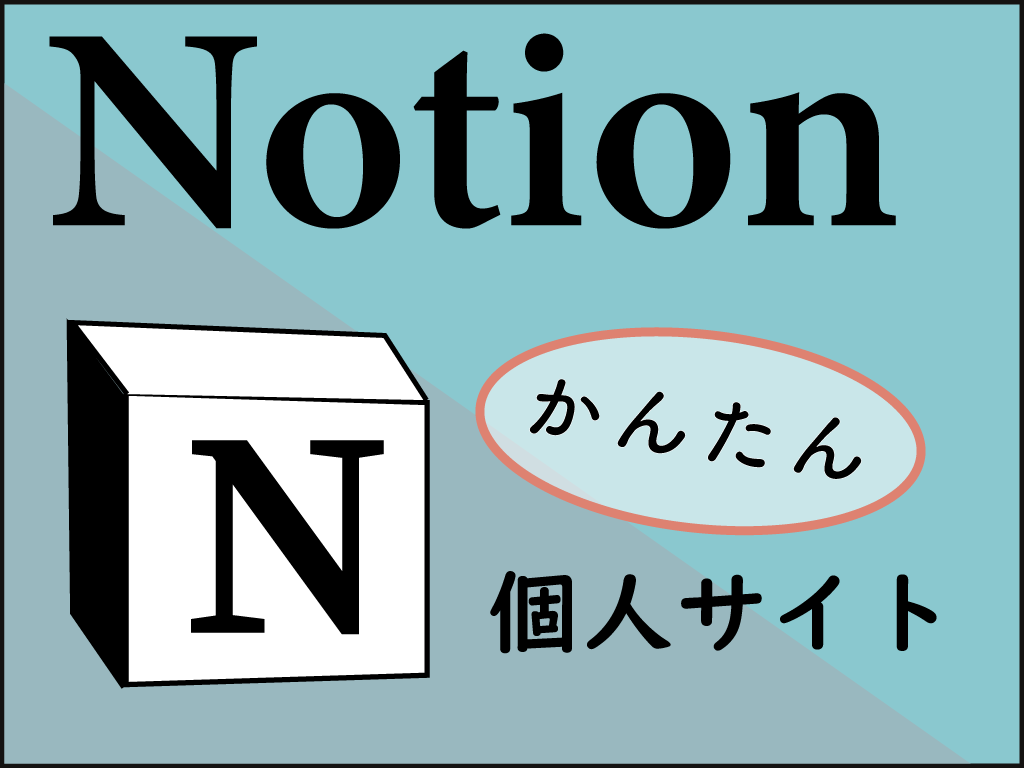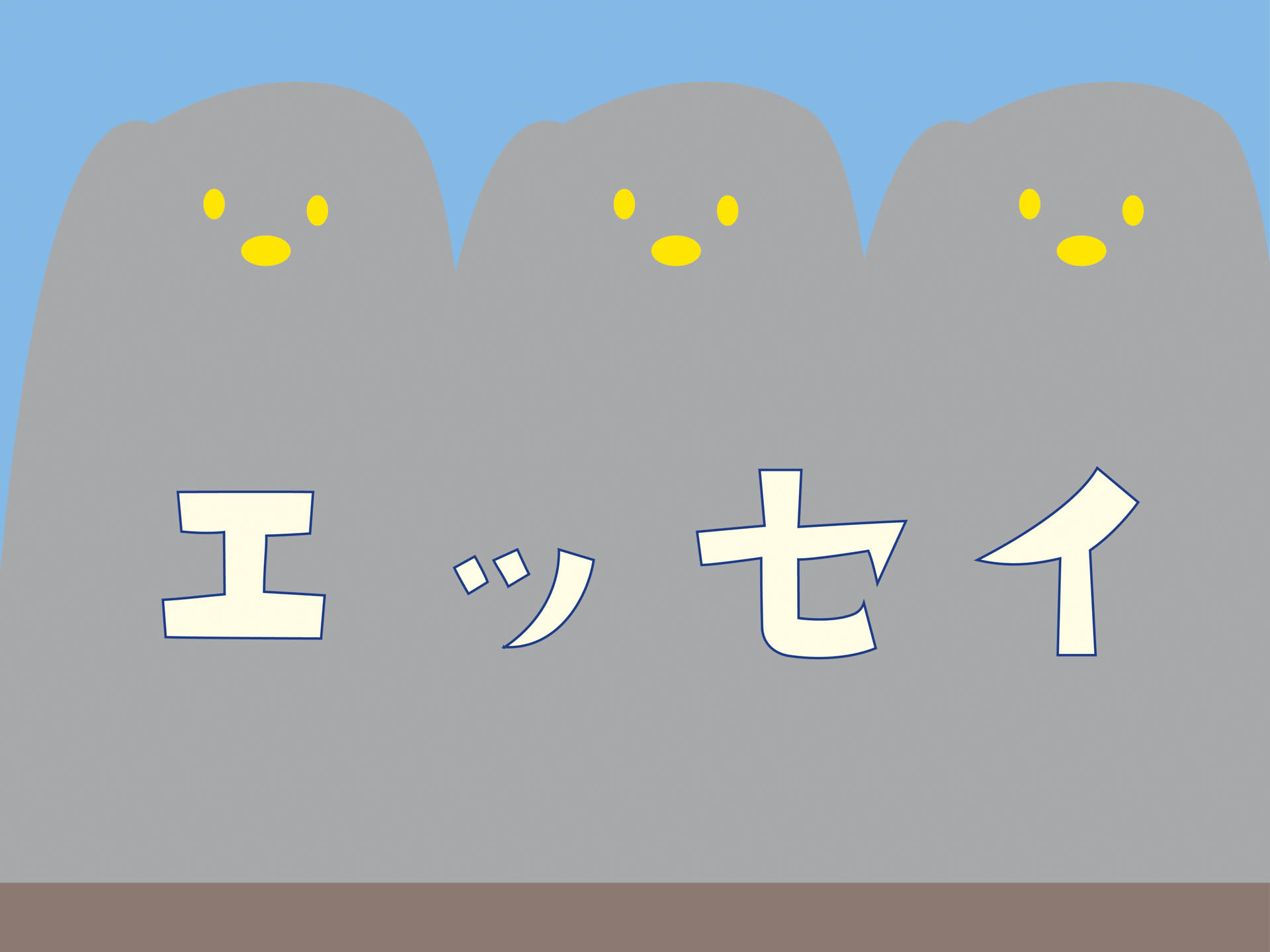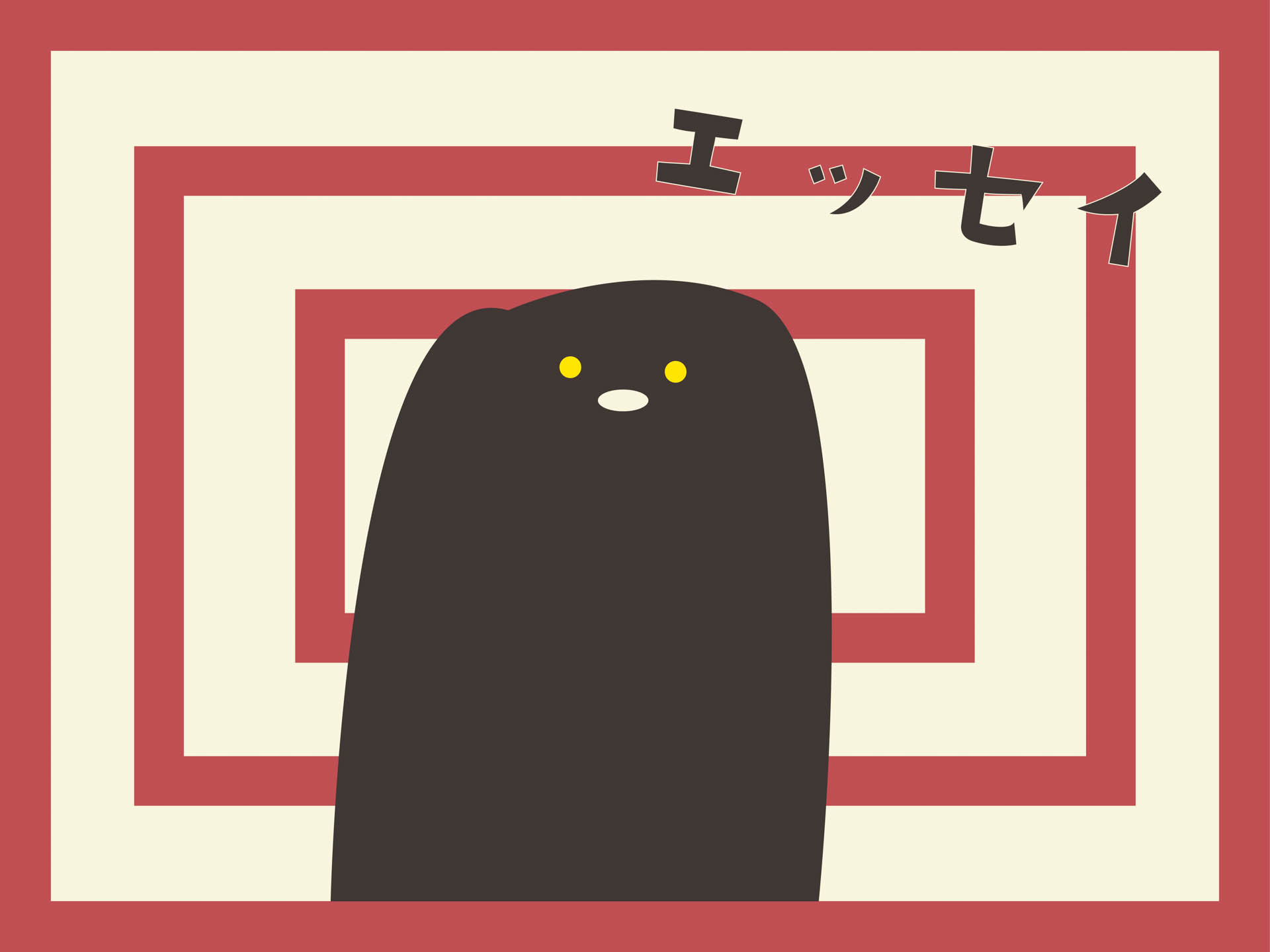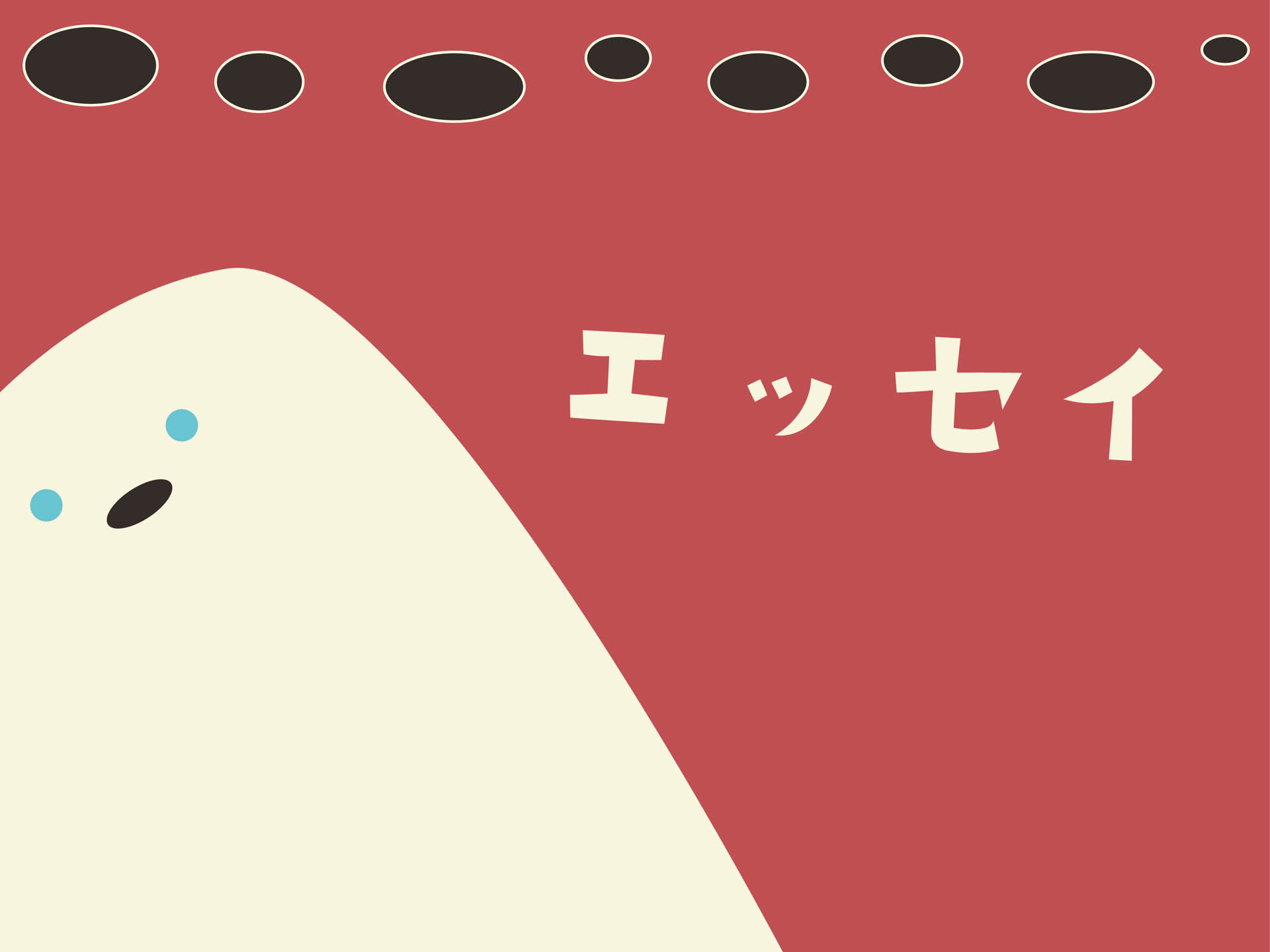同居人である夫がインフルにかかっていた。
先週木曜と金曜に出社していたので、そこでウィルスを貰ってきたらしい。
おそらく金曜の飲み会だろう。
私はさいわい感染を免れた(っぽい)が、油断は出来ない。
というか今週末は久々にデザフェスに遊びに行く。
巷ではインフルが大ブームらしいので、私自身がどこかで感染しても終わりである。
それに、私は発症は免れたが感染自体はしている可能性もある。
家で大人しくしていた方がいいだろう。
というわけで引きこもり続けている。
夫が病に臥せっていたので、取り組んでいたプログラミングの方も進まない。
自力でやろうとしたが分からなかった。
どうしようかなぁと色々考えていたのだが、突然「今こそ英語を学ぶ時かもしれない」とひらめいた。
私はいつも唐突である。
唐突と言っても、以前「Redditが面白い」みたいな記事を書いたとおり、英語圏への興味は前から持ち合わせている。
そもそも、今は情報が何よりも大事だと言われている時代だ。
インターネット上の情報の約半数程度は英語によるものである。
日本語の情報など、グローバルな視点から見たらほんのわずかに過ぎない。
実際、日本で大人気の音楽アーティストの動画再生数を見た後で世界的アーティストの再生数を見ると、そのスケールの差にびっくりする。
数十万と数千万、億の差である。
日本で人気の本のAmazonレビュー数は多いものでも大体数千程度だが、アメリカで人気の本のレビュー数は数十万とか余裕で超えている。
別に日本をdisりたいわけでなく、スケールの差を提示しているに過ぎない。
実際、世界から見た日本語というのは「日本でのみ話されているマイナー言語」である。
ついでに「漢字、ひらがな、片仮名の3種類の文字を駆使していて非常に難しい。が、情感を表現するのに長けた特殊な言語」とも言える。
美しい言語、とも言えよう。
美しい言語ではあるのだが、あまりにも特殊すぎて日本語話者が他言語を学ぶのは結構ハードルが高いというデメリットもある。
逆も然り。
日本人には日本語しか話せない人が多い。
英語の浸透率は、他先進国と比べてもかなり低い。
義務教育で取り扱ってはいるものの、授業を受けただけで英語を使いこなせている人はおそらくほぼいないだろう。
英語が話せる日本人は、大抵追加で何かしらの学習をしているはずだ。
つまり日本人の大半は世界から言語の壁で阻まれていて、国内向けビジネスは日本語が通じる人(つまり日本人)という数少ない牌(シェア)を奪い合っているということになる。
ビジネスに限った話ではない。
「多くの人に読んでほしい」と思い書かれた何気ない文章でも「この文章が日本語で書かれた」という事実だけで、世界の人から見向きもされていない。
そんな現実がある。
結局国内の読者を得るために、少ない牌を奪い合う競争に身を投じる必要があるわけだ。
最近は翻訳が優秀なので、日本語の情報を積極的に拾う英語圏の人間も、もしかしたらそこそこいるのかもしれないが。
このような視点を抜きにしても、世界的に流行っている本を日本語訳が出版されるまで読めないというのも周回遅れな感じがする。
これがグローバル視点の重要性。
それから、私はphotoshopやらイラレやらBlenderやらを嗜む。
プログラミングも少しやる。
WordPressでサイトも運営している。
海外製…主にアメリカ製のサービスとは切っても切り離せない関係である。
で、調べ物をしたい時…日本語で検索してもろくな情報が出てこない場合が多い。
英語のhowtoの方がはるかに数が多い。
ソフトウェアなどに限らず、編み物だって英語のhowto動画の方が圧倒的に多く多彩である。
これらのhowtoはぶっちゃけ英語が分からなくても何とかなるものではある。
が、英語を分かっていた方が遥かに効率が良い。
また、英語を学ぶだけで似た言語の習得ハードルはぐっと下がる。
というかフランス語あたりは英語ともそっくりで、語彙と独自ルールを追加で覚えれば大体意味を把握する事は出来るようになるだろう。
実際、英語に似ている言語はかなり多い。ルーツが同じだからである。
というわけで、英語を学ぶメリットってめちゃくちゃある…どころか、英語が分からないデメリットやばくね?となったわけである。
人生におけるデバフだ。
前置きのつもりがめちゃくちゃ長くなってしまった。
そんなわけで英語学習を始めた。
といっても、一般的な参考書は一切用いていない。
とりあえずRedditの日本旅行の旅程相談スレッドから英文を引っ張ってきて、まずGeminiに和訳してもらう。
それから英文と訳を比較しつつ、Googleドキュメントで色分けしていく。
色分けはSVOCだ。授業でやらされたアレである。
意味さえ捉えられればいいので、厳密な文法に沿ったSVOC分けは最初から目指していない。
というかRedditのような場だとみんなカジュアルな言い回しである。
かっちりした文法の型に分けようとしても、上手くいかない場合が多い。
苦戦。
しかしこの過程で気付いた事がある。
「長い英文というのは、シンプルな英文を接続詞やカンマ、コロンで繋ぎ合わせた文章に過ぎない」という事である。
and, so, but, or, if…
他にもたくさんあるが、こういった言葉を最初に見つけ出すのが長文を楽に読む鍵なのではないか?と思った。
前提1、前提2、言いたいことの核。
If だった場合、or の場合、私は⚪︎⚪︎したい。
こんな感じで、複数の文章が接続詞で繋ぎ合わされて一つの文章にまとめられている。
まとめられる段階で冗長な主語は省略される。
だからこそ「まずSとVを探せ」という従来のSVOC分けを長文に適用しようとして、つまずく人が後を絶たないのである。
従来の文節分けだと接続詞は大抵オマケ扱いされるが、接続詞を最初に探し出して色分けした方が、読解の効率が圧倒的に良くなる事に気付いた。
全然オマケじゃねえ。
そもそも「一見複雑なものを分解してシンプルに捉え直せ」というのは、論理的思考法の基礎基本である。
という感じで、これを発展させて独自のメソッドを編み出してしまった。
勝手に「ブロック分解学習法」と名前もつけた。通称ぶぶ法。
このやり方を早速実践しているが、従来の文節分けよりも圧倒的に理解度が上がっている。
書き手の意図がよく分かるようになった。
もはや学習というよりパズルゲームをやっている感覚である。
Geminiに英文を共有しつつ、
「この文章はsoの後が言いたい事の核なんすね」
「このwhichは主語と接続を兼ね備えてるからこそ万能…だから関係代名詞って特殊な扱いなのかぁ」
と、言語学の領域に踏み込みかけている。
楽しくて他の事など見向きもしない。
つくづく私は研究者気質なんだろうなと思う。
このメソッドはいずれブログ記事で詳しく書ければいいなと思う。