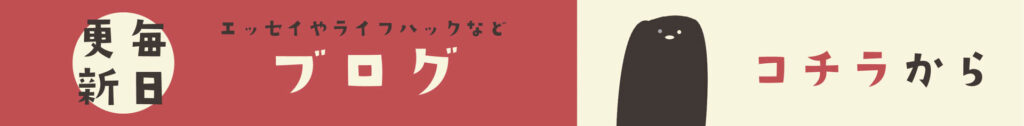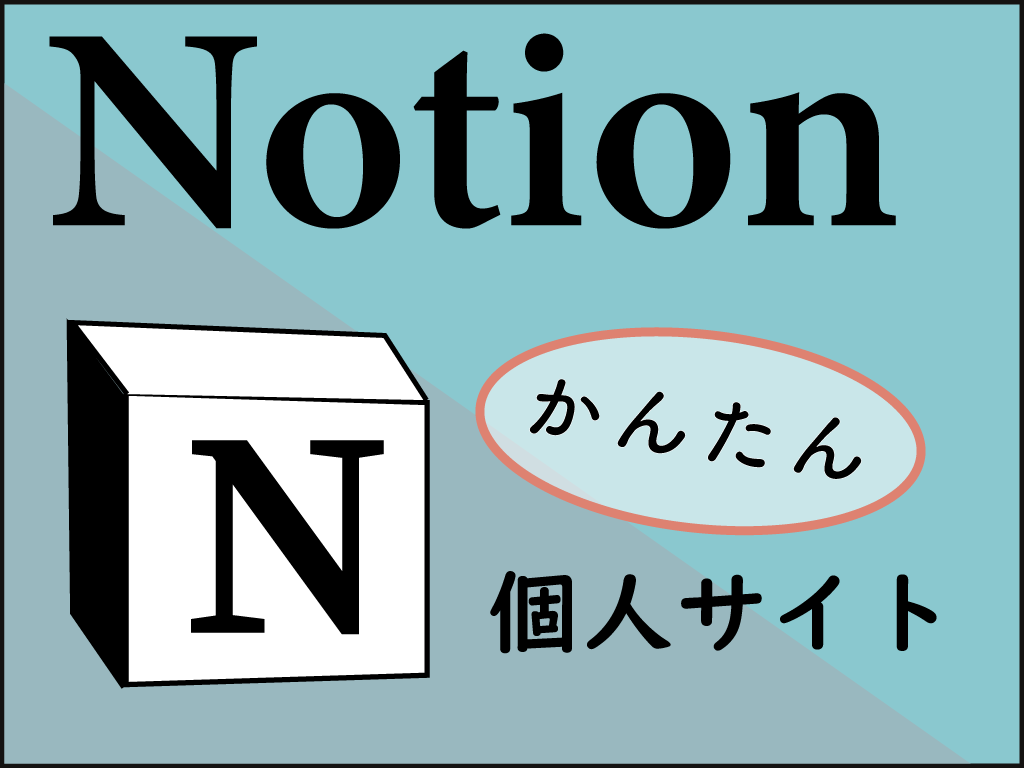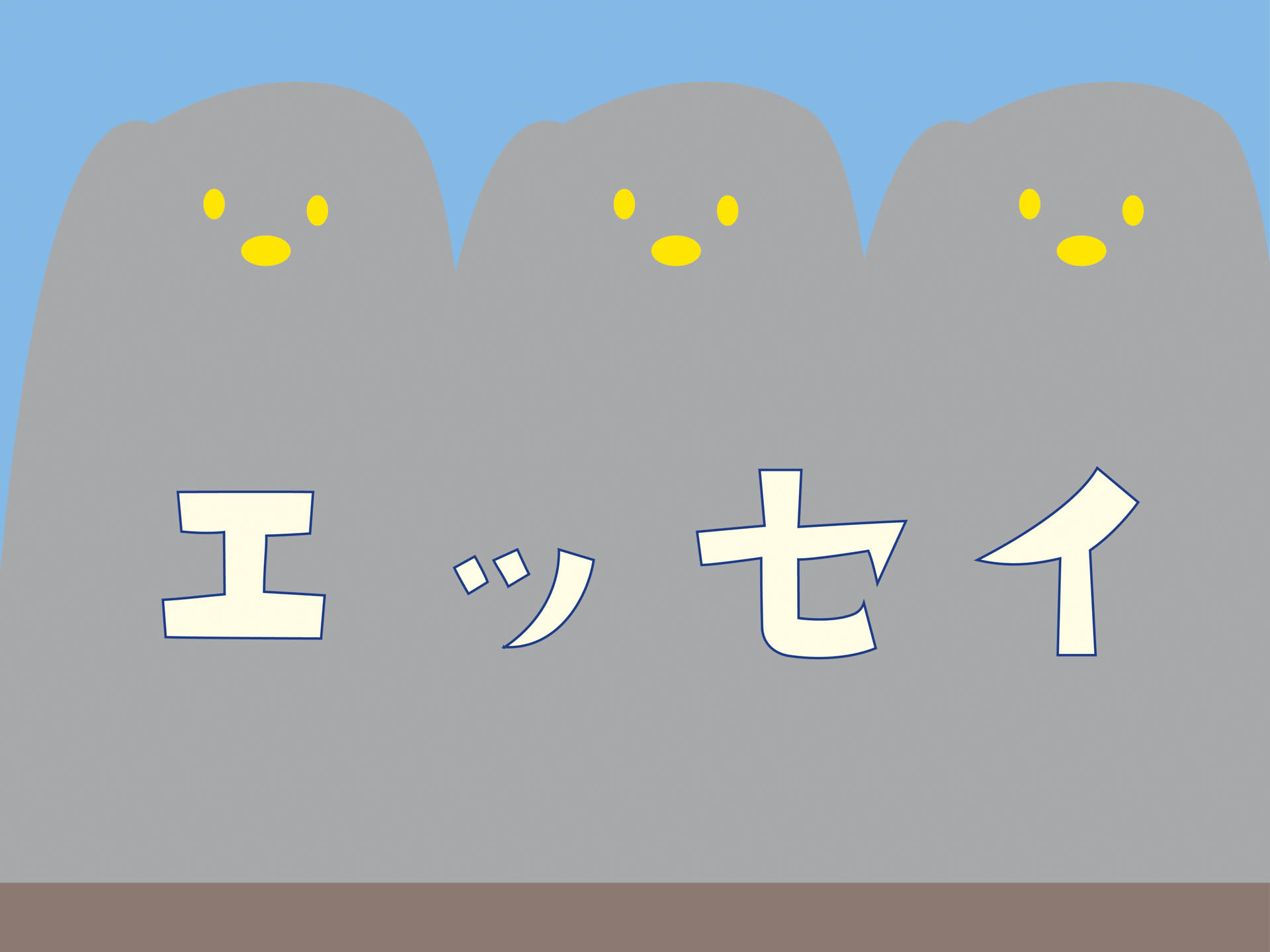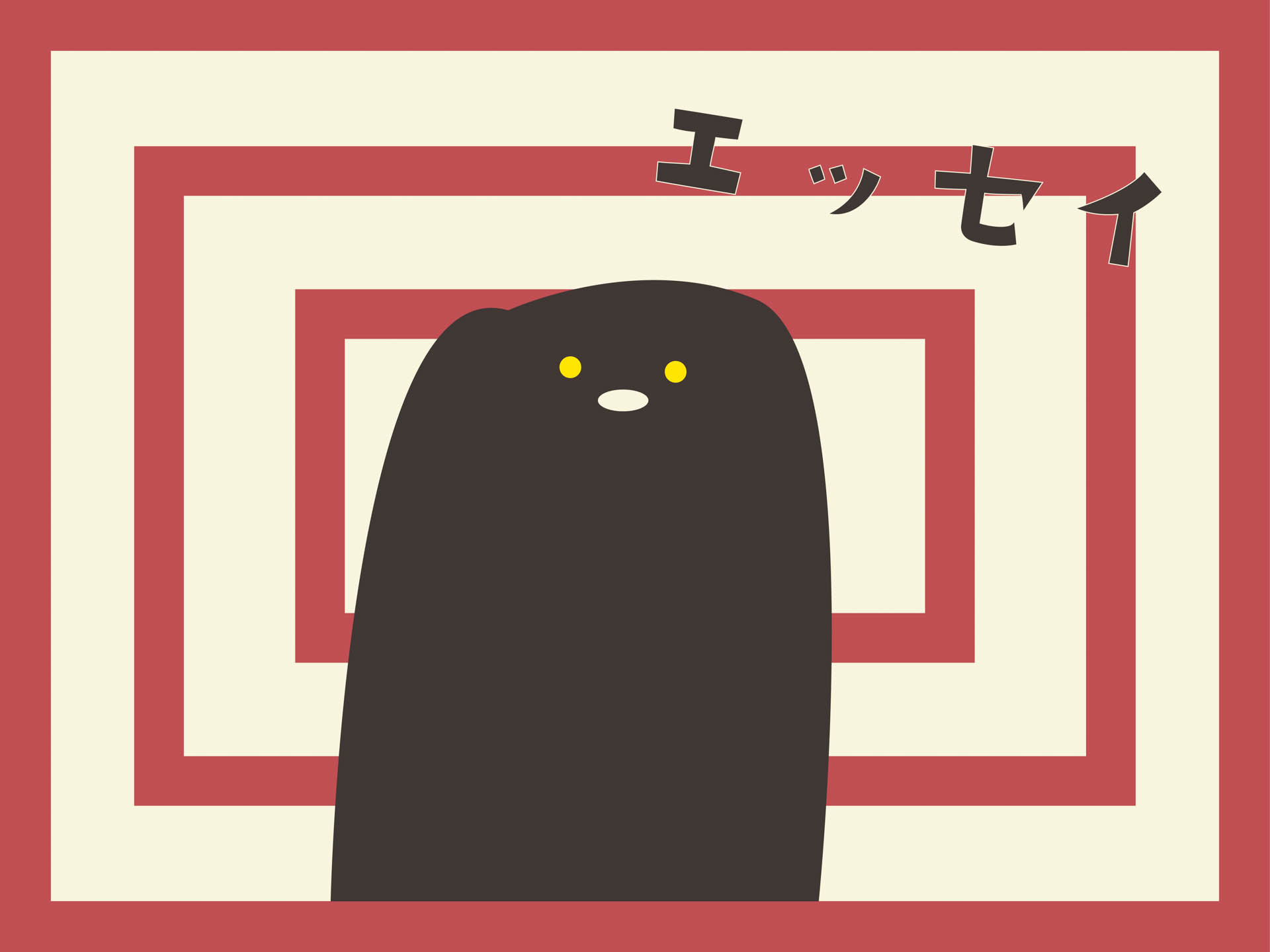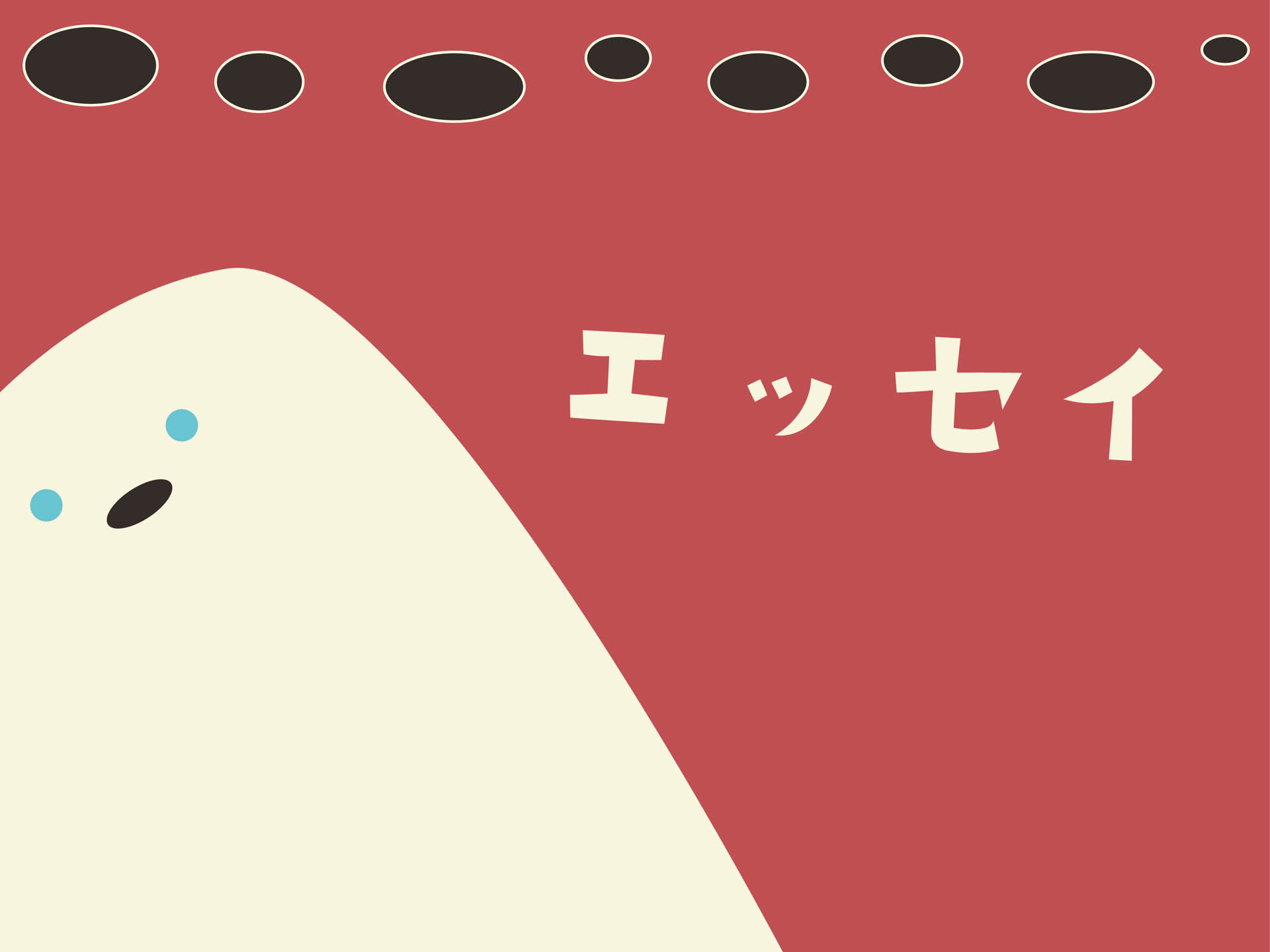2025年5月9日にnoteで公開した記事を移行したものです。
昨日はAudibleでこの世のあらゆるエネルギーを解説する本を聴いていた。
といっても堅苦しいものではなく、何も知らない人でも気軽に読めるタイプの本だ。
聴きながら色々考えていた。
雷は電気である。
現代では当たり前の事だ。常識。
しかし雷が電気だと判明したのは1752年。
ベンジャミン・フランクリンの実験によるものである。
それじゃ昔の人は雷を何だと思っていたのだろう。
電気自体は古代ギリシャからあったので、科学者達は何となく「あれは電気だろうなぁ…」と思っていたかもしれない。
じゃあ一般人は?
昔は学校に行けない人もたくさんいた。
そんな彼らは雷の事をどう思っていたのだろう。
神の怒り?雷神?
昔は避雷針も無かったんだから、雷にうたれて死んでしまった人も、今よりたくさんいたかもしれない。
現代でさえ部活の練習中に雷にうたれて…みたいなニュースをたくさん聞くし。
こう考えると、昔の人にとって雷ってかなり畏れ多いものだったんじゃないかなと思う。
雷に限らず、昔は不思議なことで溢れていたのではないだろうか。
地震だってそう。
今なら地面のプレートの動きというのを誰もが知っているが、昔の一般人がそんな事を知る由もない。
地下を大蛇が這っているなんていう、現代なら荒唐無稽な説話でも信じてしまうだろう。
昔の人がやたら宗教にハマってた理由も分かる気がする。
このように当時としては原因不明の怖い事ばかりで、祈らなきゃやってられなかったんだろう。
現代はかなり科学技術が発達した。
今の時代に「雷や地震は神の怒りなんだ!」とか言ってる人がいたら、リテラシー低いなぁ…変な宗教ハマってる人?と思われるだけである。
とはいえ、今の科学じゃ説明出来ない事もまだまだたくさんある。
死んだらどうなるのか?は最大の謎ではないだろうか。
死にたくない、死が怖いという人はたくさんいるし、逆に天国に行きたい、死んだら楽になると考えている人もいる。
死なんて無じゃない?と考えている人もいる。
いつか科学技術で死というものが何なのか、死ぬとどうなるかが説明出来る日が訪れるんだろうか。
そんな壮大なものじゃなくても、身近なものだと気圧による不調。
最近では気象病という言葉も定着してきた。
なんかよく分からんけど身体が重い、頭が痛い、古傷が痛む…。
気圧の乱高下でこういった事は起きがちだが、つい最近までは「なんかよくわからんけどしんどいな…」と思ってた人がたくさんいたはずだ。
私もその1人である。
その謎の現象に気象病という名前がついた。
そのおかげで前もって痛み止めを飲んだり、気持ちが楽になった人もたくさんいるはずである。
科学というのは本質的に、不思議な事を体系化して名前をつけていく行為なのかもしれない。