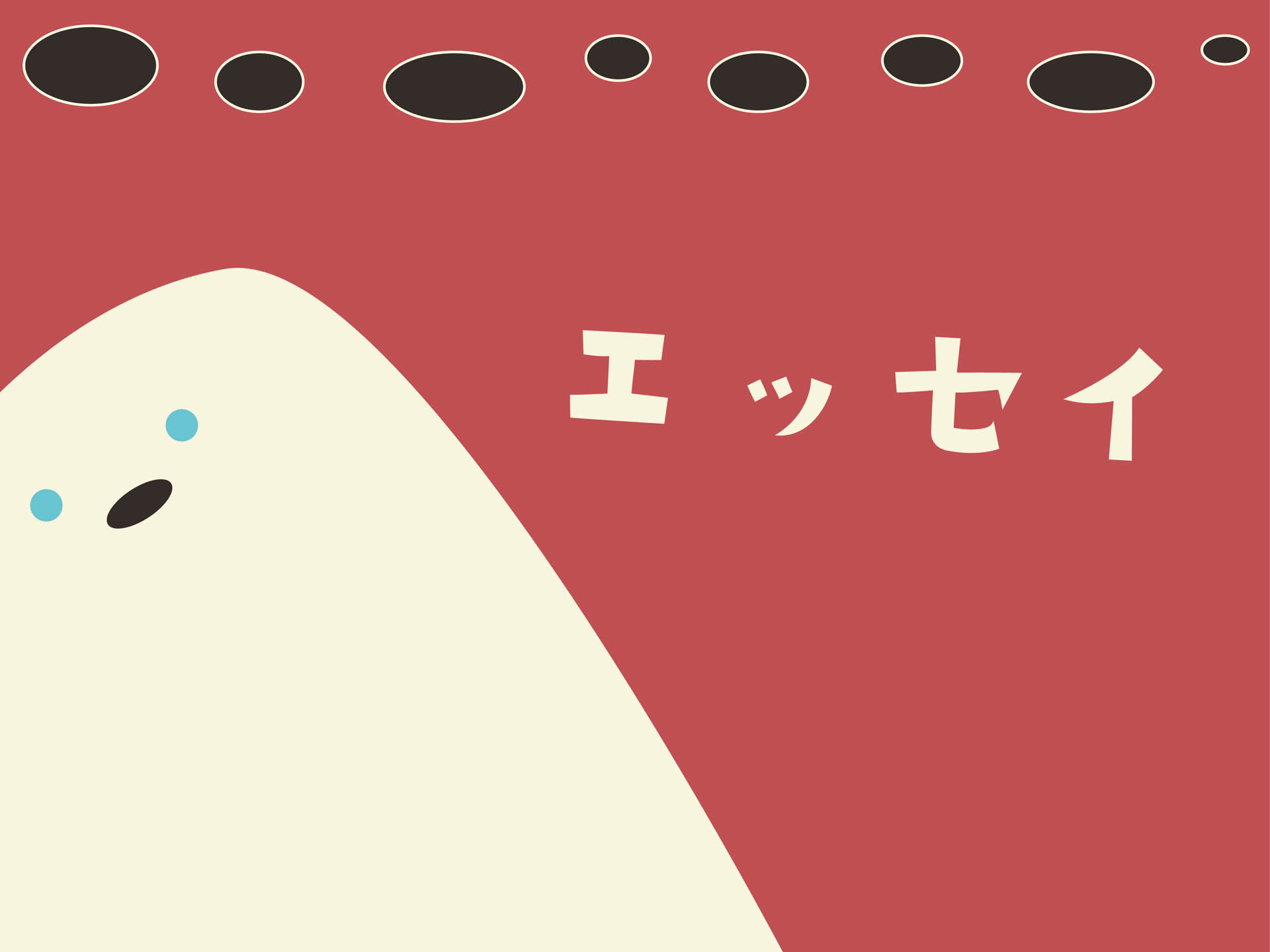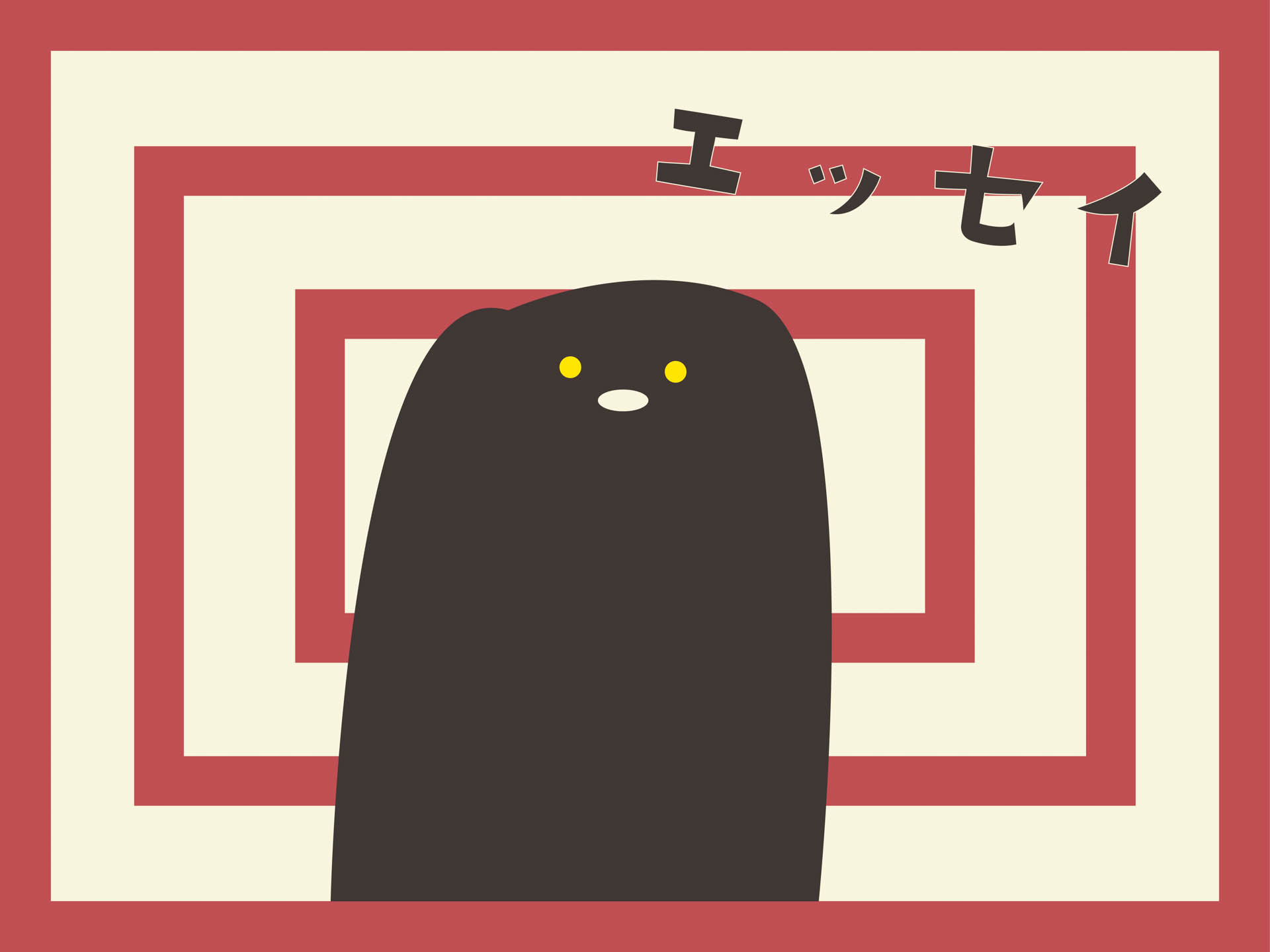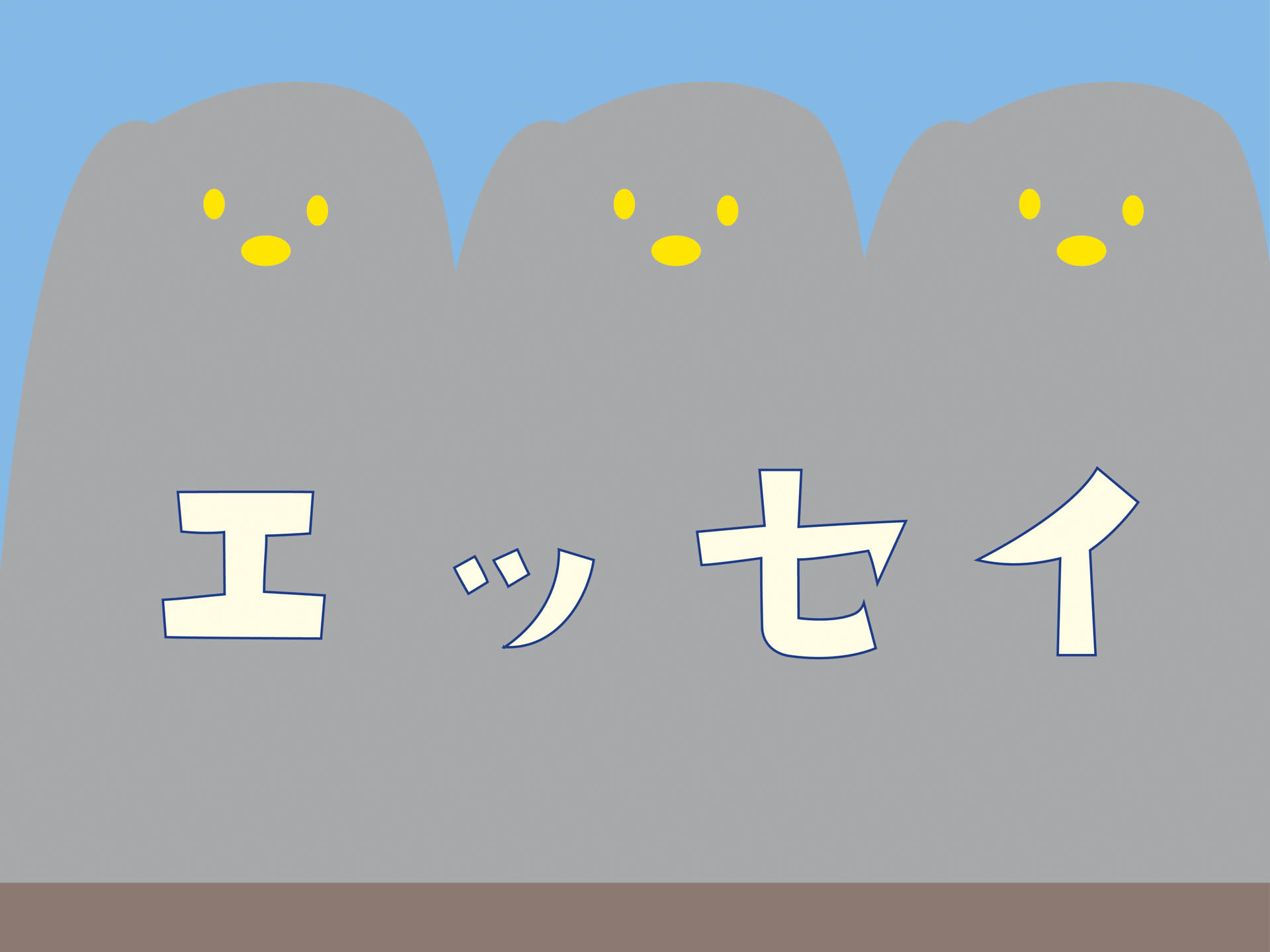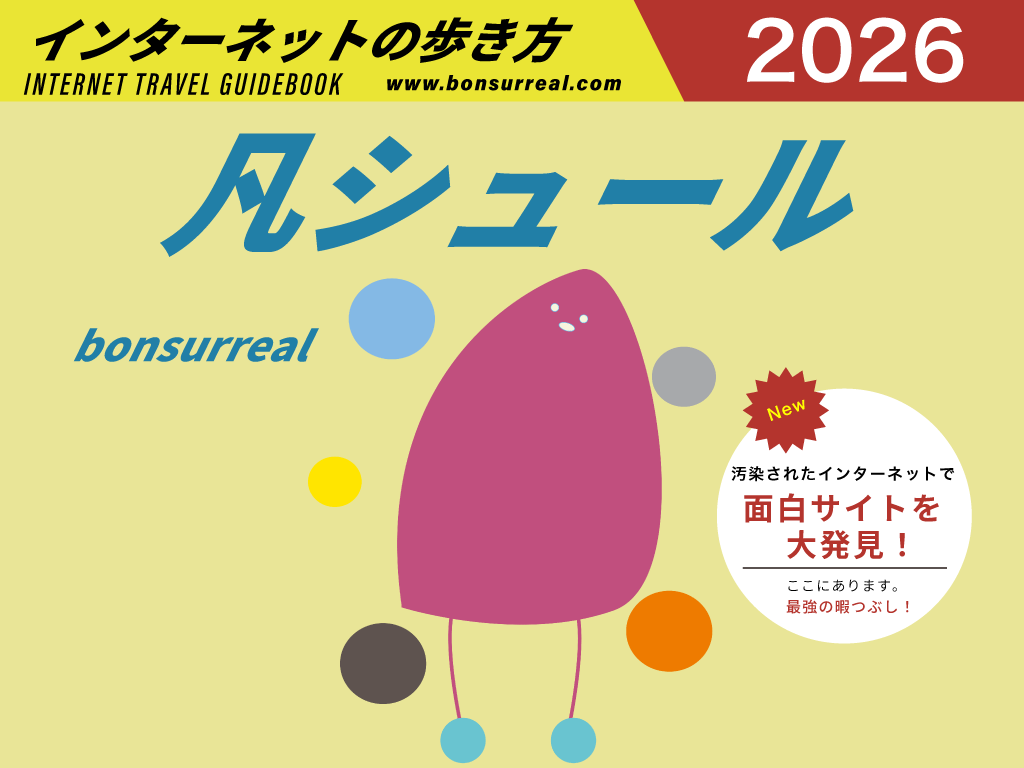久々に編み物をした。
編みかけだったあみぐるみのボディをひたすら編んでいく。
個人的に無心で編んでいく方が好きなので、細かいパーツ作りやパーツを繋ぎ合わせるのはあまり得意じゃない。
が、今回はそこまで抵抗なく完成まで持って行けた。
不恰好さを受け入れる覚悟が出来たからなのかもしれない。
最近色々な民芸・工芸品に触れてみて思ったが、よくよく細部を見ると思ったより不恰好な物もたくさんある。
糸処理が雑だったり、左右のバランスがちょっと悪かったり。
多少歪んだり失敗したからといって、その物の魅力が薄れる事はない。
アンバランスさに勝る魅力があるからだ。
むしろ少し不恰好な方が、手仕事としての味が出るのかもしれない。
そう考えたら、いつもより気楽にパーツを縫い合わせる事が出来た。
不揃いだからこその魅力。
これは手仕事にしか出せないものだ。
アナログならではの味。
AIにはなかなか出せないものである。
AIもアナログっぽい絵を描く事は出来るが、あくまでも「っぽい」だけだ。
不揃いという記号を捻出しているだけ。
「アナログっぽい不揃いな絵」と指示すると、不揃いさを演出した絵が出てくる。
絵自体の出来は悪くない。
が、なぜだろう。
人間が描いた絵のような、遊び心が無いんだろうか。
見てて思わず笑みが溢れてきそうな何かが足りない。
ふーん、結構いい出来じゃん。これだけだ。
というわけで、AIの絵自体に感性は内包されていない。
が、AIの絵をトリガーにして鑑賞者の感性を呼び覚ますことは可能だと思う。
作者の感性がその絵自体に無いからこそ、多くの人に普遍的な感性を呼び覚ます機能はあるわけだ。
例えば「ふるさと」の絵。
「ふるさと」は多くの人にノスタルジーを感じさせる普遍的なテーマである。
絵をトリガーにして鑑賞者は「ふるさと」を想起する。
こうして鑑賞者の感性を呼び覚ます事は可能だ。
つまりAIイラストを見て人間が「ふるさと」を思い涙する現象は大いにあり得ると言える。
AIイラスト自体に感性は存在しないが、鑑賞者の感性のトリガーにはなりうる。
このあたりが混同されているから、AIイラストに関する議論は複雑さを増しているのだろう。
結論を言うと、AIイラストが美術のいちジャンルとして存在するのはあり得るが、人間の作品を淘汰する事は不可能だという事になる。
産業革命が起きても手仕事が完全に消滅しなかったように、写真が主流になっても絵画を描く人が消えなかったように。
と、編み物からうっかり生成AIについてまで思いを馳せてしまった。
ちなみに私は、AIイラストは個人的には好きでない。
あくまで趣味嗜好の問題だと心得ているが。
やはり私は作品自体が大いに感性を持っている美術作品が好きという事なのだろう。
今までは技術ばかりが礼賛される時代だったが、これからの時代はAIの台頭により、正反対の不揃いさが評価される時代になる気がしなくもない。
というよりは評価も多様化していくのだろう。
AI側も人間に寄せる進化…
つまり不揃いなど感性の要素を模倣しようとするのではなく、理性の究極美を突き詰める方向に進化した方がいいと思う。
感性を模倣したところで人間の感性を超える事はないだろう。
AIが理性担当、人間が感性担当となる。
適材適所だ。