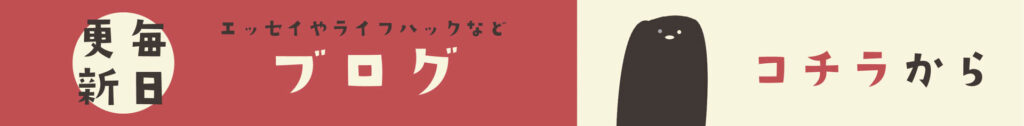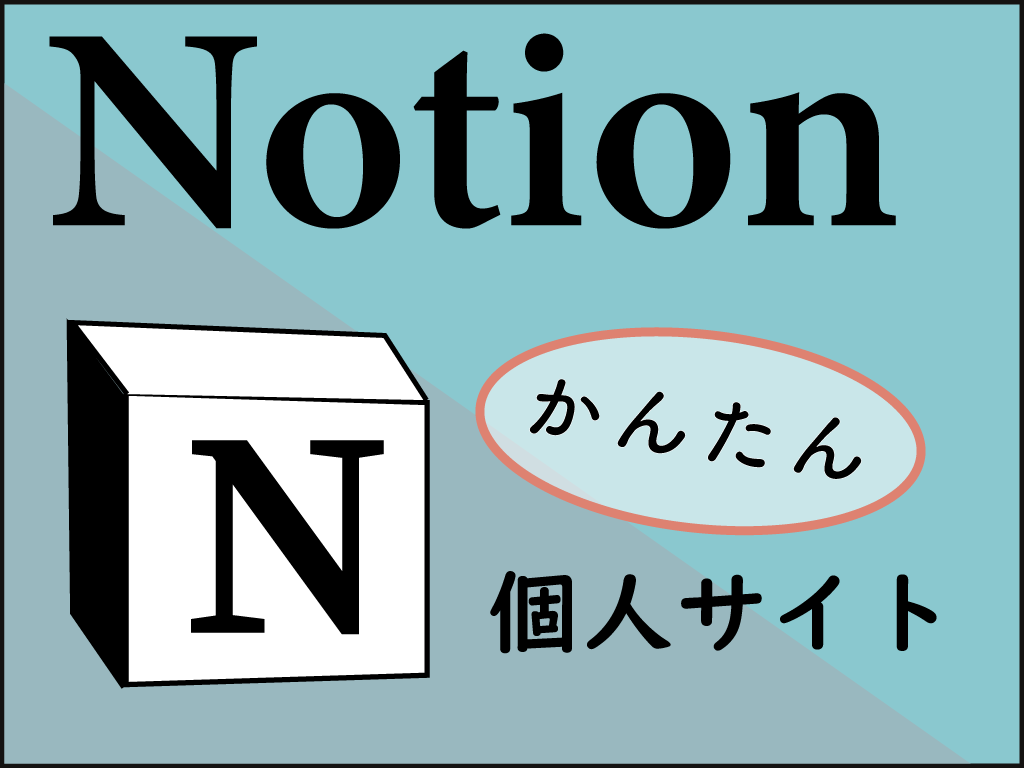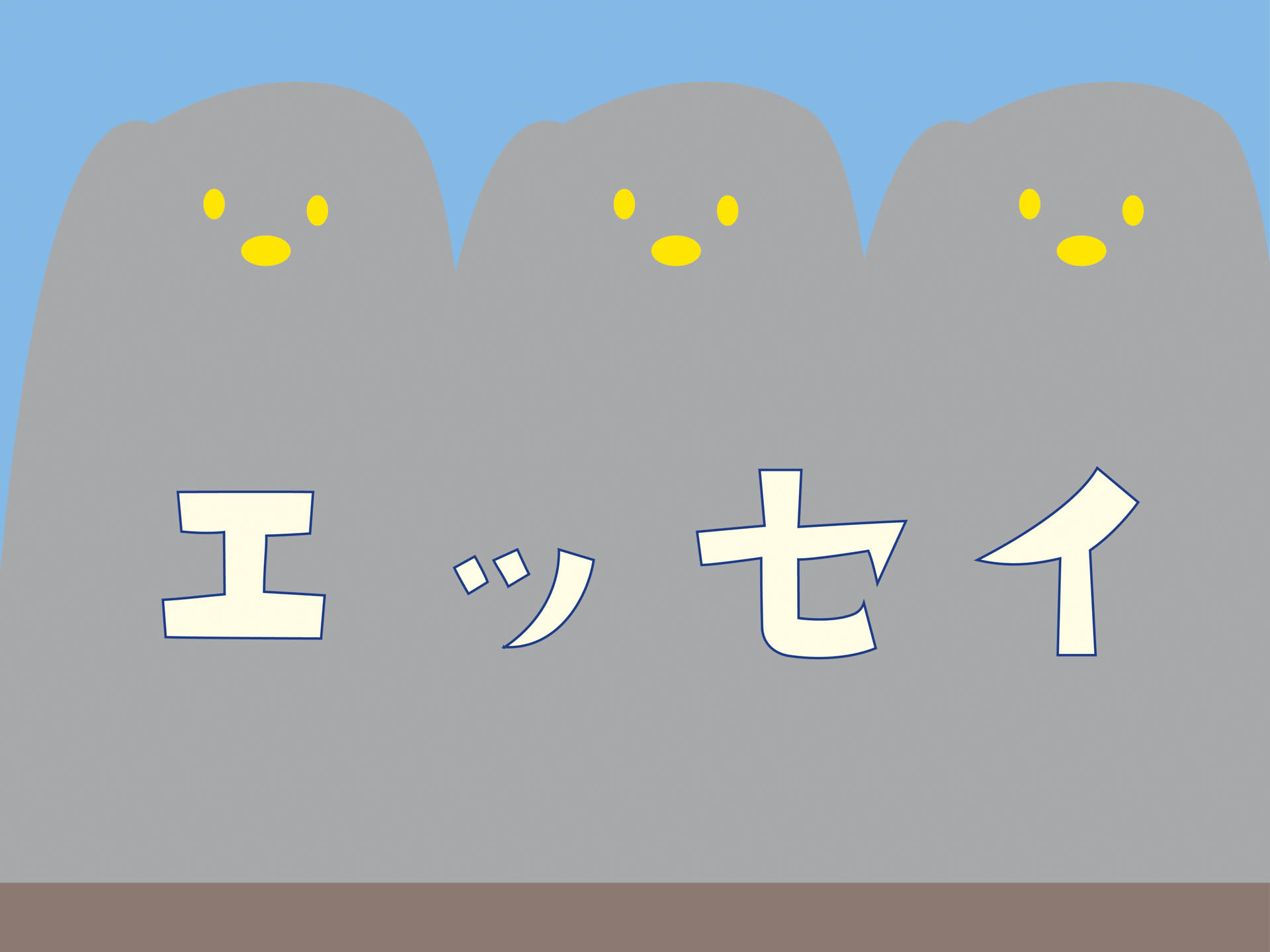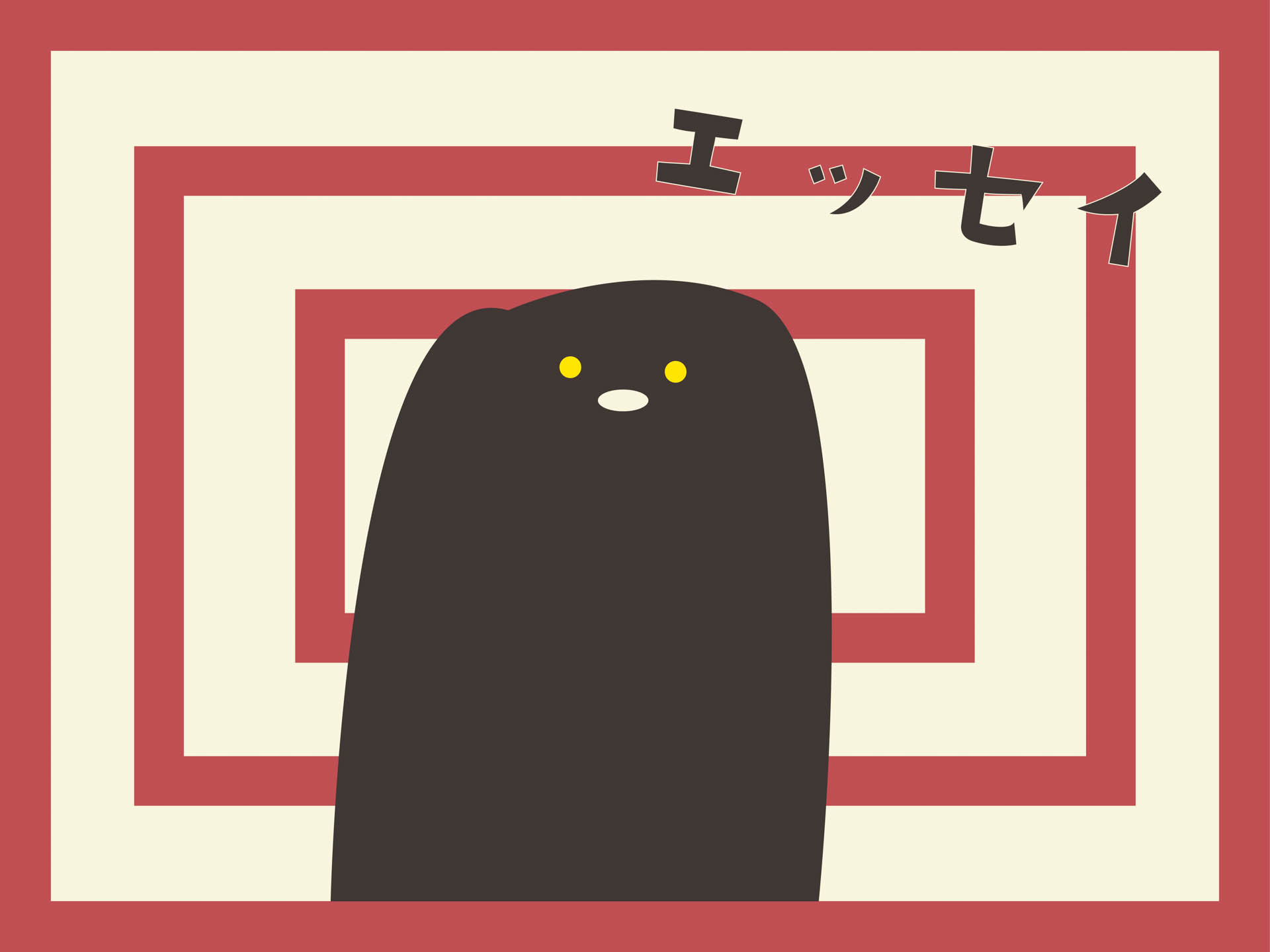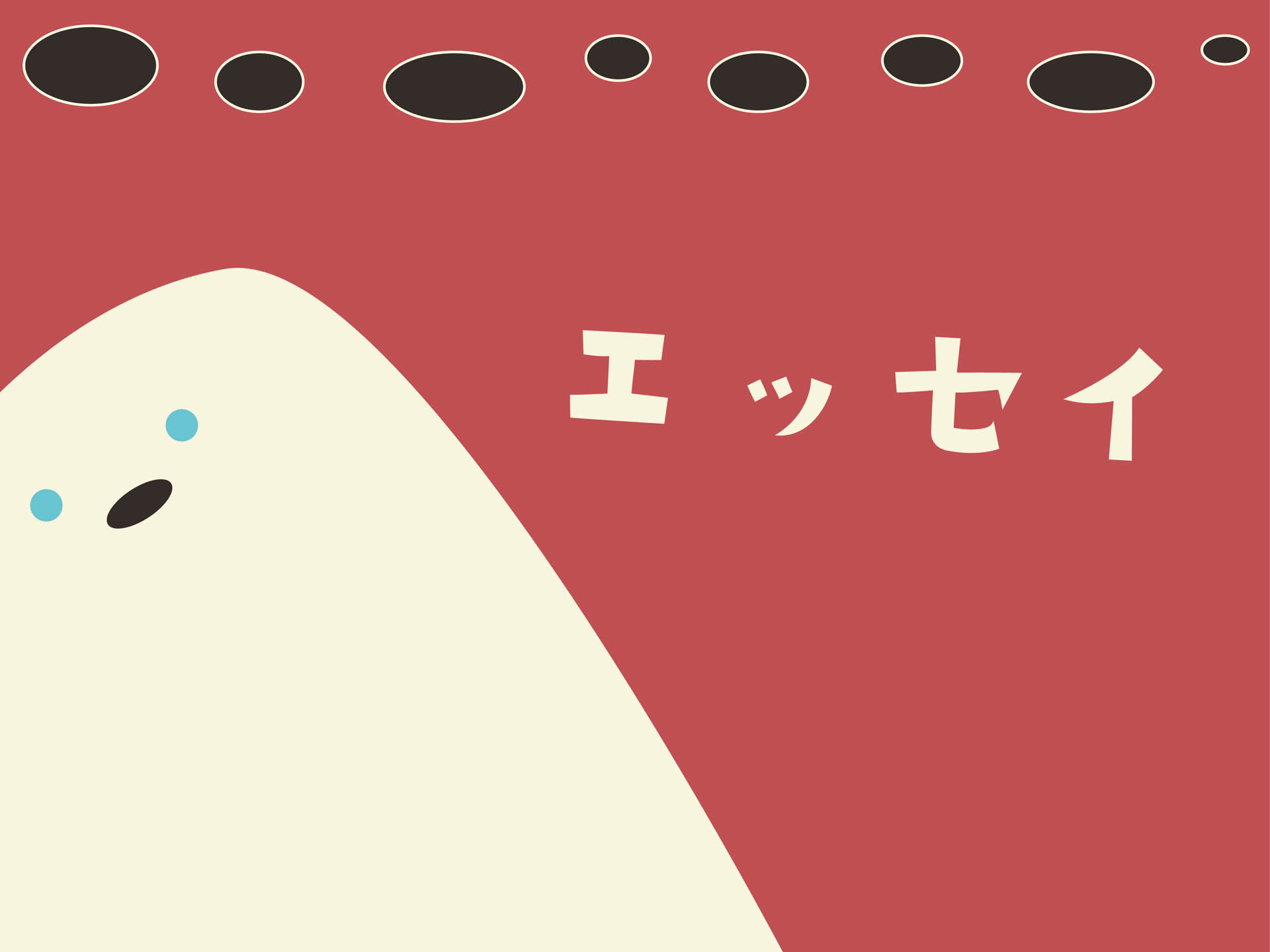2025年4月16日にnoteで公開した記事を移行したものです。
世の中の人間は理性型と感性型に分けられると思う。
この理性型と感性型、まず文字の認識方法が違う。
理性型は文字を情報として認識し、感性型は文字を感情として認識する。
このようにざっくりと二分してみたが、理性型は理性100%で感性0%、感性型は感性100%で理性0%などと言い切るつもりはない。
極端な二元論は嫌いだ。
Aさん:理性70%、感性30%
Bさん:理性20%、感性80%
Cさん:理性90%、感性10%
配合は人によって変わるし、一生この割合を維持するというわけでもないのだろう。
状況によってもコロコロ変わるかもしれない。
現在の私は理性40%、感性60%といったところだろうか。
もともと感性寄りの人間だが、この記事のように抽象的な感性というものを言語化出来るという強みもある。
理性型は文字を読む。そのままの意味だ。情報としてのみ受け取る。
感性型は文字を感じる。書き手の温度や意図を感覚で受け取る。
ひどいニュースを見て心を痛めるかそうでないか。
太宰治の人間失格や斜陽を読んで「メンヘラの文章だな、よくわからん」と評するか「刺さりすぎて引きずられそうになった」と評するか。
自然の風景に癒されるかそうでないか。
伏線回収されない映画に「説明不足だ」と感じるか「余韻がある」と感じるか。
音楽を聴く時、曲を重視するか歌詞を重視するか。
感性のリトマス試験紙はそこら中にある。
よく「男女の感覚の違いによりケンカが起きる」例として、話を聞く時にアドバイスを求めるか共感を求めるか?がある。
男性はアドバイスするし、女性は共感する、といったものだ。
これを男女の性別で分けるのはナンセンスで、単に理性型なのか感性型なのかの差に過ぎない。
男性の方が理性型が多く女性の方が感性型が多いという傾向はもしかしたらあるかもしれないが、それはわからない。
仮にあったとしてもそういう傾向があるに過ぎない、という話である。
理性に偏りすぎると融通の効かない、面白みのない人間になる。
哲学者カントとかまさにそれ。
感性に偏りすぎると何かフワフワした事言ってる電波キャラ的な人間になる。哲学者プラトンとかそうじゃない?イデアって何だよ。
結局カントは理性100%を目指せ!と言っていたに過ぎないし、プラトンも感性100%を目指せ!と言っていたに過ぎないと思う。
ようするに「人間やめろ」である。
結局、理性50感性50が理想なのではないだろうか。
人間らしさ、感性の揺らぎを持ちつつもそれに飲み込まれずバランス良く保つ。
今の社会はカントの影響が根強く残ってるというか…。
一応多様性を大事にしよう!など感性も重視する流れは来ているが、まだまだ口先だけだなと感じる場面も多い。
マーケティング分野は理性が重視されていると思うが、感性が全く分からない人間には不可能な分野だなと思う。
顧客が真に何を求めてるか分からない、感性の無い人間が商売なんか出来るわけない。数字だけでは語れない部分だ。
私がよく言う「人間じゃなくて数字ばかり見てる」とはまさにこの事なのだろう。
感性に支配されるのも良くないが、理性の支配も良くない。
では上手く共存させるべきなのではないか。
それが人間らしさの追求なのではないかと思った今日この頃である。
追記(2025年6月25日)
ジェネリック理性感性論。
カントの部分は当時の考えなので訂正が必要かもしれない。