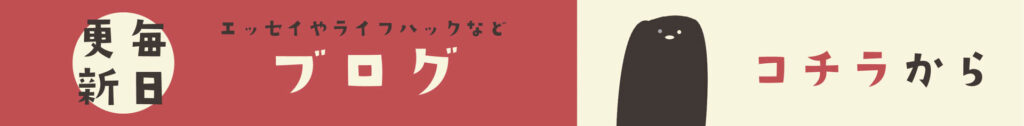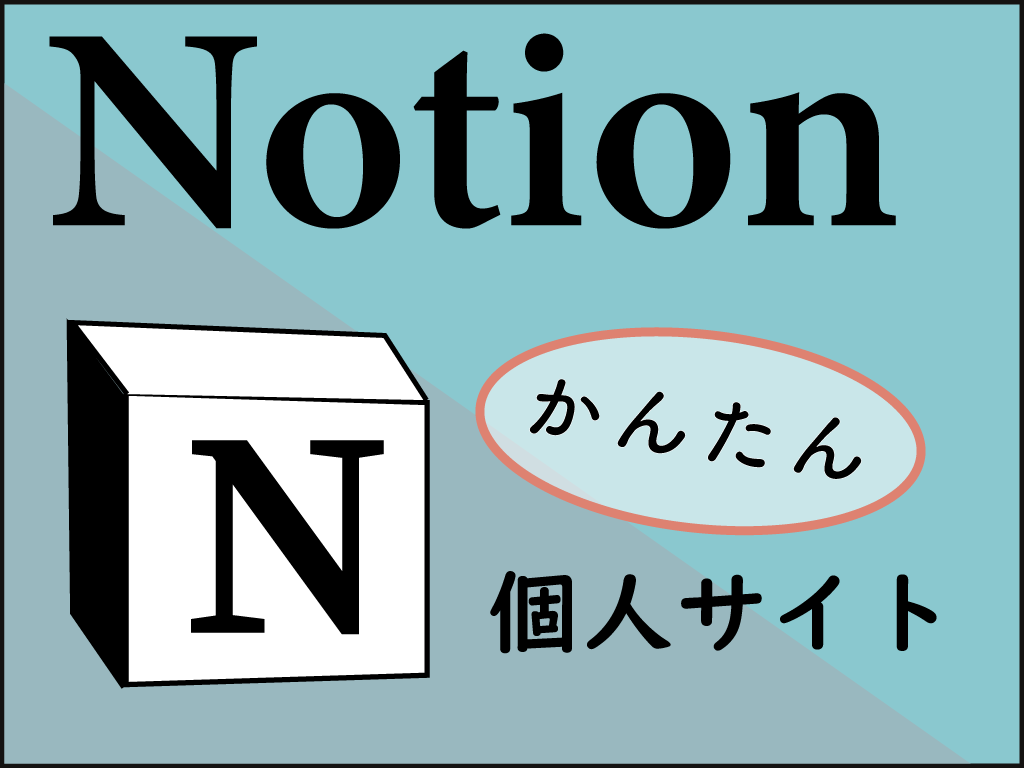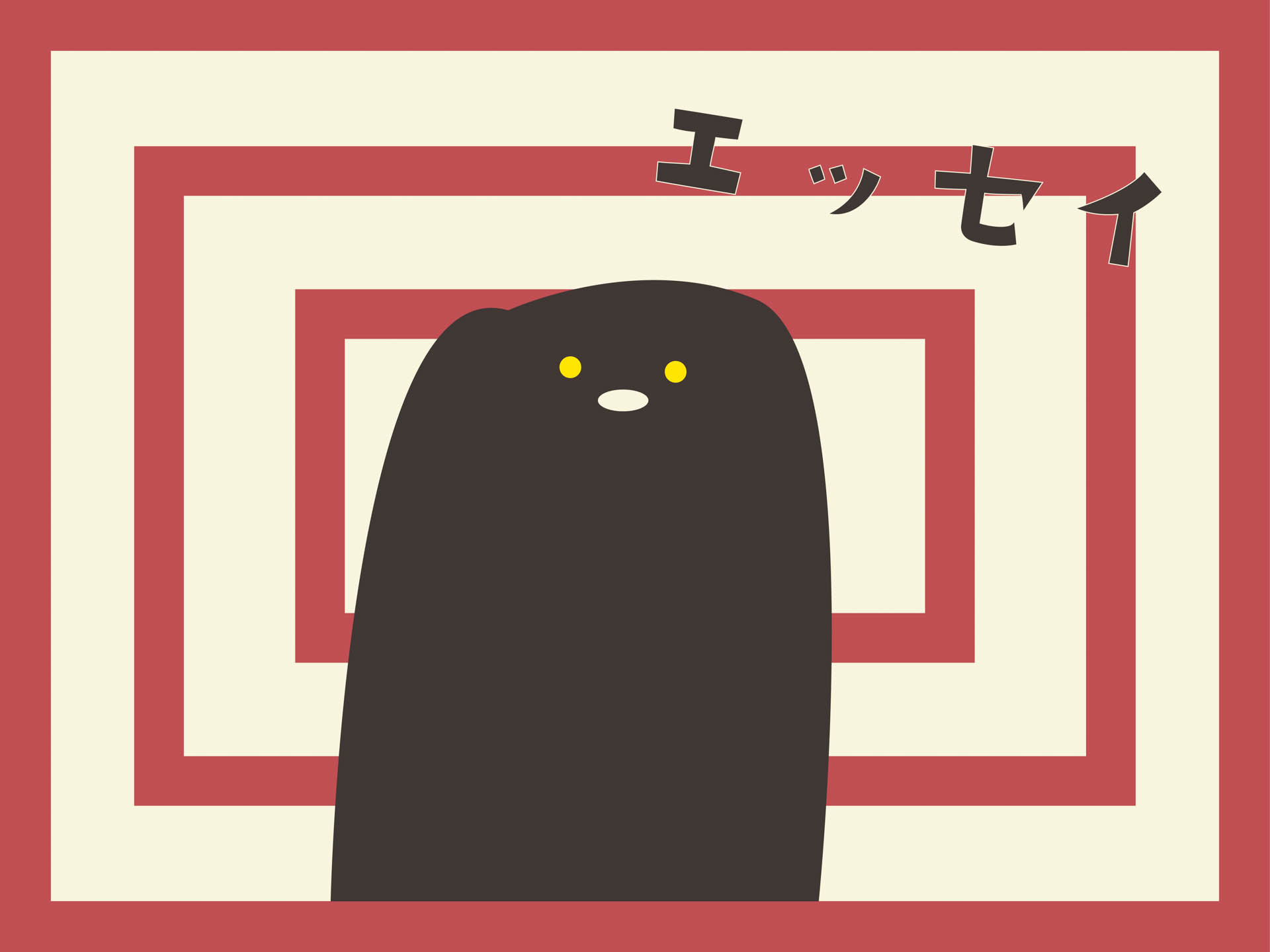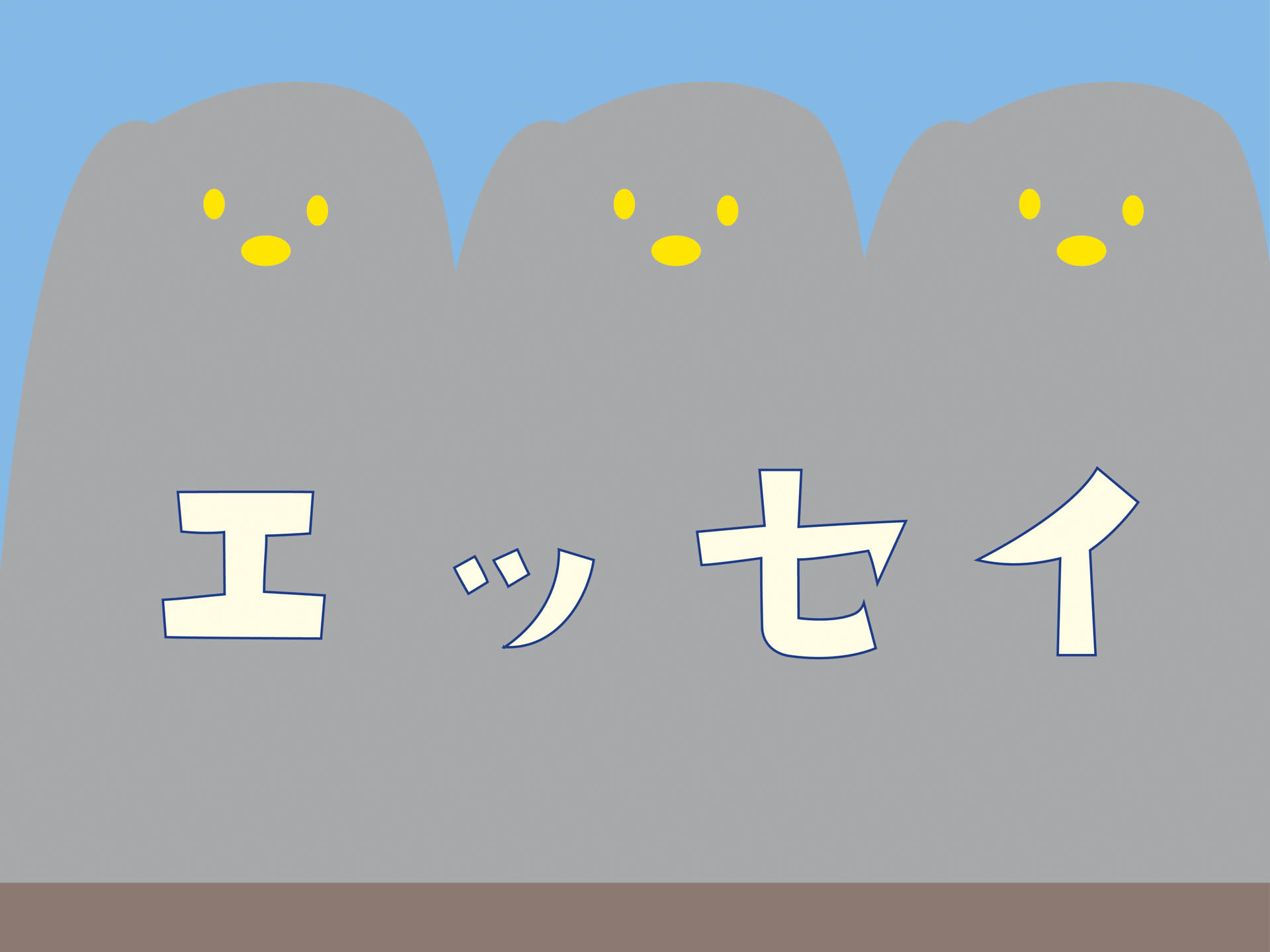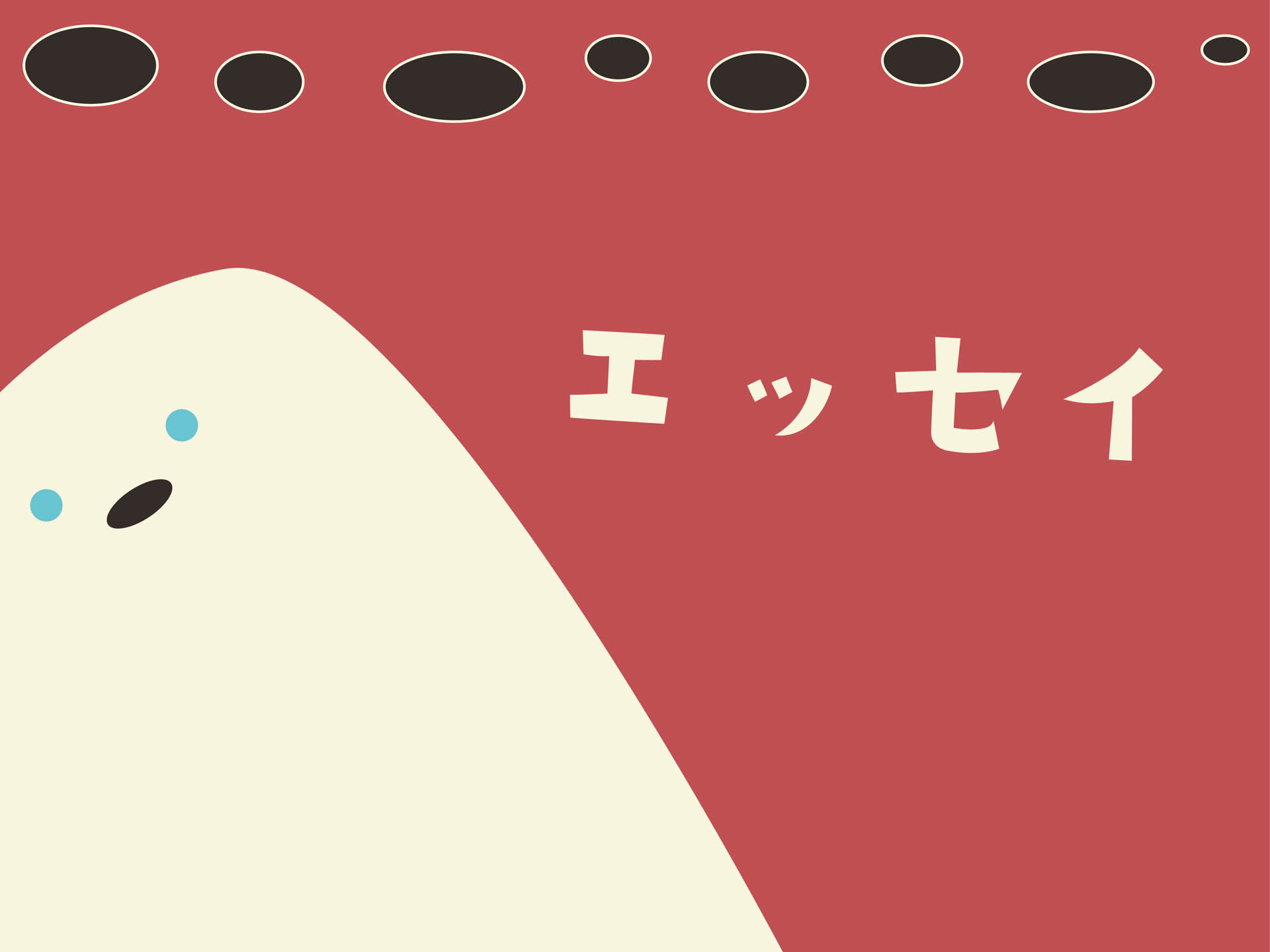2025年3月6日にnoteで書いた記事を移行したものです。
ここ3日ほどDTMをやっていたが、ようやく短い曲が出来た。
1日目
Ableton Liveの設定
MIDIコントローラーの接続
2日目
Medlyのデモ曲をAbleton Liveでそのまま打ち込む(とにかく操作に慣れるため)
3日目
打ち込んだデモ曲をチップチューンアレンジする
そのアレンジからメロディとベースを改変してオリジナル曲作成
といったプロセスだった。
イラストも作曲もそうだが、やはり模写を改変してだんだんオリジナルにしていくやり方が良いと思う。
こういう時は料理に例えるとわかりやすい。
料理初心者に「レシピとか全く見ずに料理を創作してください」と言ってもまあ作れないと思う。
大抵みんな既存のレシピに忠実に従って作っていると思う。
そこから「味は濃いから醤油を少し減らそう」とか「にんにく足しちゃおう」と自分好みにアレンジする。
「キャベツを使う料理だけど白菜の方が安いから白菜に変えちゃおう」
これでだいぶ違う料理になる。ここまでいったらオリジナルレシピと言ってもいいだろう。
玄人になると、食材を見ただけでオリジナルレシピを生み出す事も簡単になるだろう。
創作も基本それと一緒の流れだ。
それなのに、創作だと「1からオリジナルレシピを作ろう!」みたいな空気が蔓延してる気がする。
パクりと言われるのを恐れているからかもしれない。
なので初心者だろうが玄人並の事をやらされる。
根気が無ければ挫折する。それが今の創作界隈だと思う。
パクりの定義を履き違えている人が多いのかなと思う。
料理と一緒で最初は既存レシピの真似でも、どんどん自分好みに改変していけばオリジナルになるのである。
素人がいきなり1からクオリティの高いものを作れるわけがない。
模写なりして、既存のものがどういった構造になっているか学ぶ。
その技術を自分の中にインストールする。
どんどん改変していってだんだんとオリジナルにしていく。
これが創作分野の効率的かつ挫折しづらい学習方法である。
模写とはいっても、既存の作品をそのままコピーしたいわけじゃない。
それこそパクりになってしまう。
あくまで構造とか技術を学び取りたいだけだ。
だからイラスト模写する時は極力情報量を落とす。
いわゆる「ゆる絵」にアレンジしてしまう。
パーツがシンプルでありながら、ゆる絵だって一つの完成形だ。
そのまま模写すると情報過多だが、ゆる絵にすることでそのキャラクターと認識するために本当に必要な情報だけ浮き彫りにする事が出来る。
パーツがシンプルになるので模写が楽になる、というメリットもある。
今回の作曲作業でまず既存曲をチップチューンアレンジしたのも同じ理由だ。
チップチューンとはいわゆるファミコン時代のゲームにあるようなピコピコしたBGMだ。
楽器は3つだけ。メロディ、ベース、ドラムのみの超シンプル構成。
その3つだけでもしょぼくならないのがチップチューンの凄いところである。
情報量を削ぎ落として、余計なものをなくした方が色々と理解しやすい。
曲をチップチューンアレンジする過程で、もともと細かく動いていたノーツが煩わしく聞こえる部分もあったので、思い切って消してシンプルにした。
だいぶ改変はしたものの、チップチューンアレンジを作った時点ではまだオリジナル曲とは言えない状態だった。これではアレンジに過ぎない。
ここからオリジナルにするにはどうすればいいんだ?
散々頭を捻った結果、メロディを一旦全て白紙にした。
で、いい感じにメロディを置いた。ここは完全に感覚でやった。
それからベースをメロディに合うように改変しまくった。
ドラムはそこまでいじらなかった。
そうしたら「あ、できたな」となった。
ひとまず何とか曲は出来た。
ここからどうするか。
この曲にまた情報を加えてチップチューンじゃないverを作るのも勉強になるかもしれない。
あと5曲作って1曲を約10分間ループさせた計1時間の作業用BGMを作るのが目標だ。
作業用BGM動画を作りたいので、ひとまずAfter EffectsとPremiere Proの使い方も勉強しようかなと考えている。
完全にゲーム感覚でやっている。楽しい。
そのせいか最近ゲームを全くやらない日も増えた。
息抜きは読書で賄っている。
最近読んでるのは銀河英雄伝説。1巻の時点で面白い。
追記(2025年6月24日)
結局この時作った曲はあとから聴いたらいまいちに感じたので、一旦ボツにした。
でも作り方の方向性としては間違っていないと思う。
2021年頃、さんざんイラストの初心者講座に翻弄されたからこそここまで手法を確立出来たんだと思う。