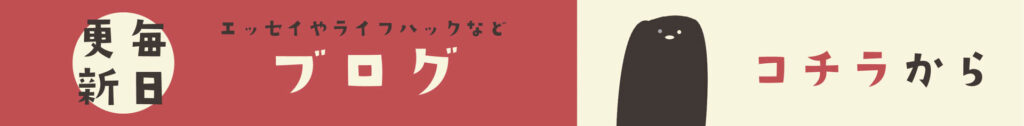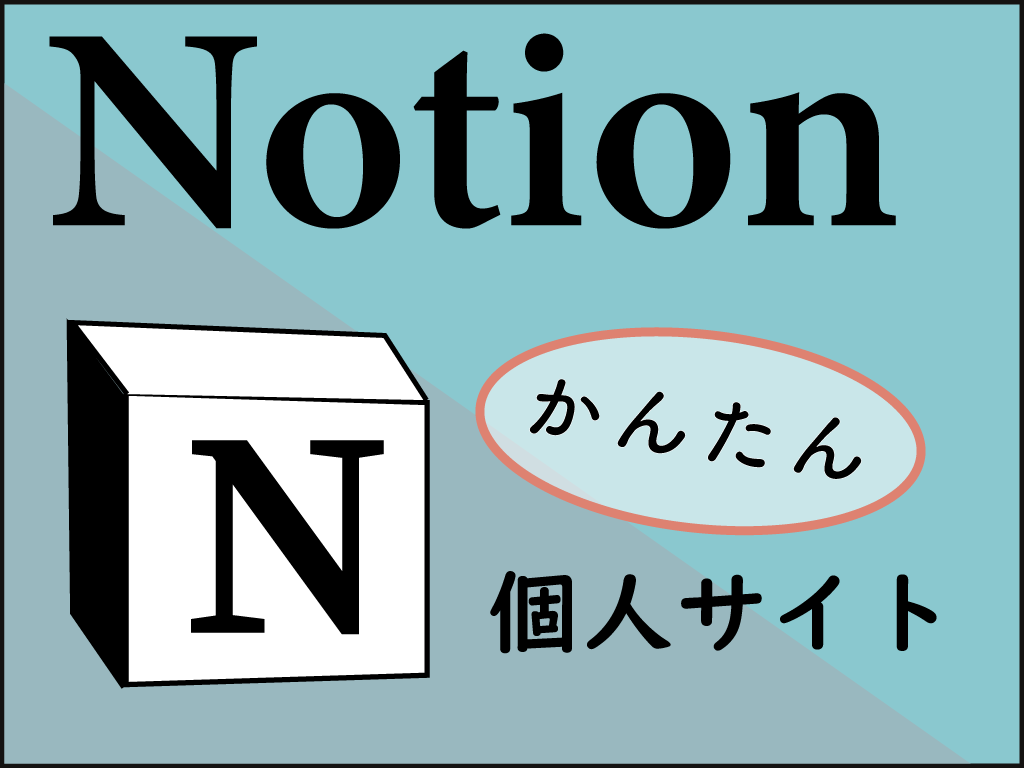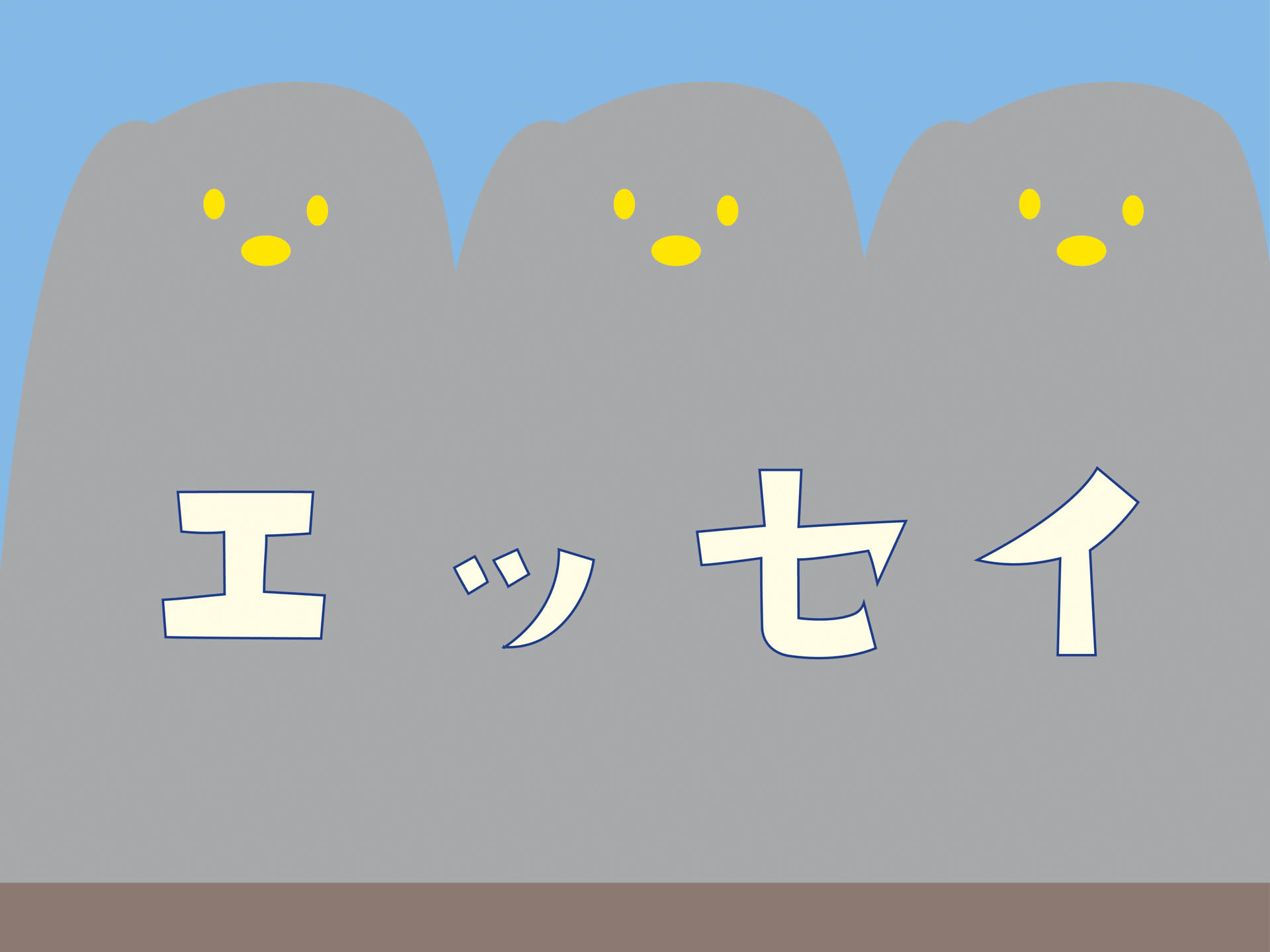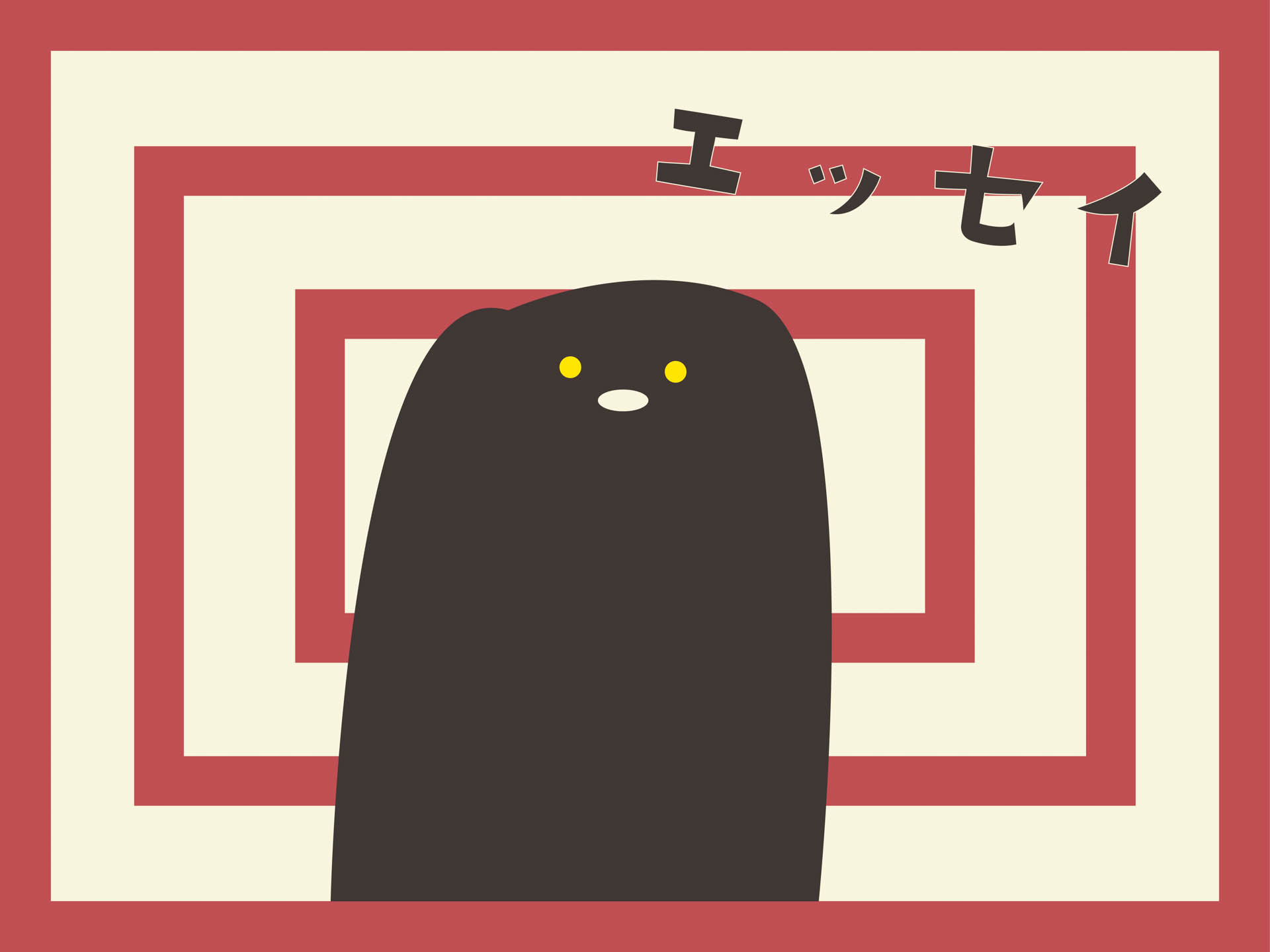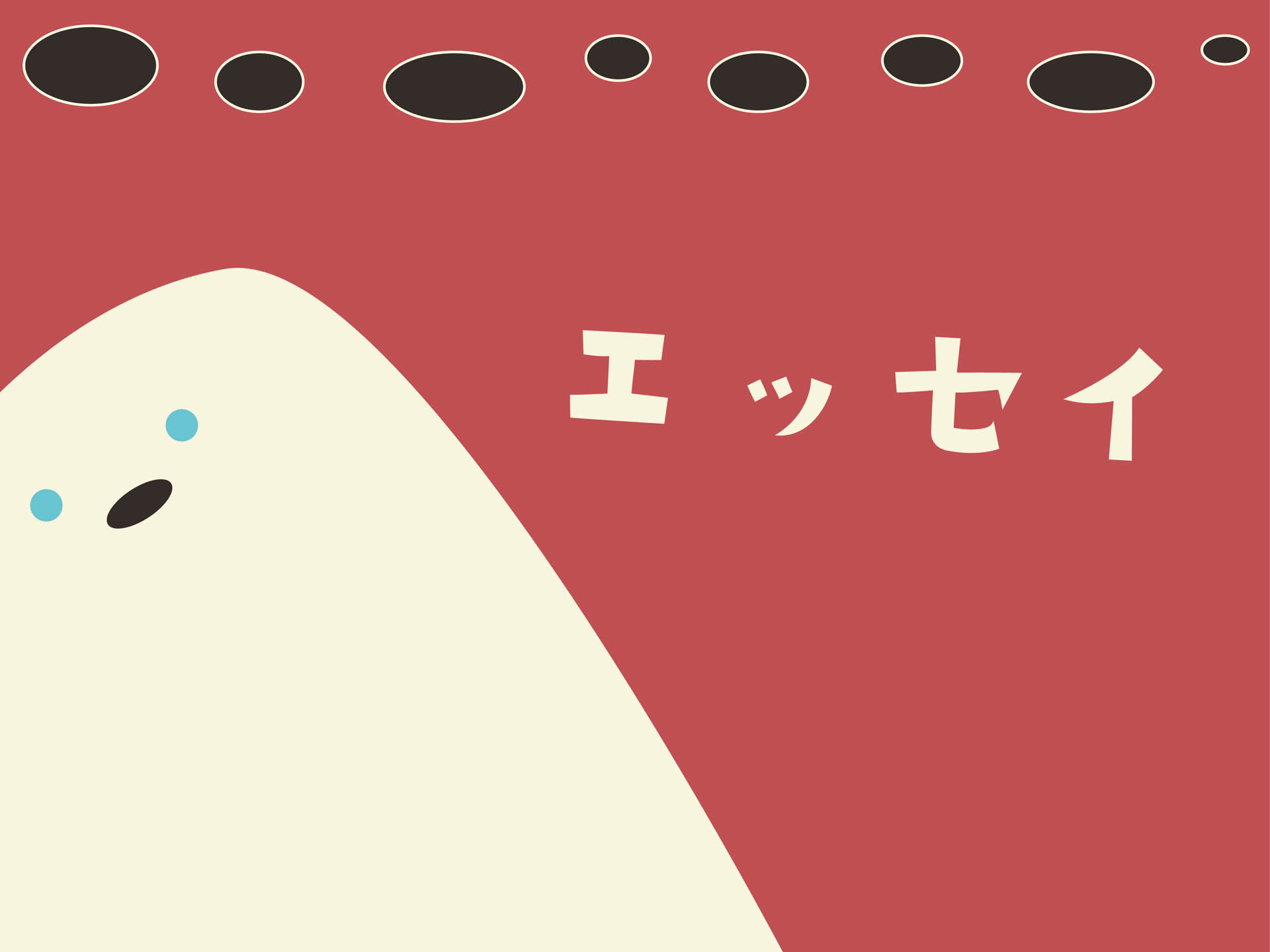この記事は、SNSが疲れる理由とどこを改善するべきかを具体的に挙げた記事となっています。
SNS疲れ、SNS離れという言葉を目にすることも増えてきました。
なぜ疲れるのか?構造に問題があるのではないのか?という批判記事です。長いです。
1.数字による極端な成果主義
SNSは数字で溢れています。
フォロー・フォロワー数、いいねの数、リポストの数…。最近はインプレッション数も可視化されるようになりましたね。
ただ日常の何気ない事を共有したかっただけなのに、インプレッション大正義ゲームに巻き込まれてしまったような感覚があります。
バズる発言とバズらない発言という格差が生まれてしまったように感じます。
なぜインターネットでまで格差を感じなければならないのでしょうか。
2.無差別で流れ込んでくる情報への疲弊
SNSのタイムラインは基本的にフォローしている人の発言が全て流れてきます。
例えば、あなたはAさんというイラストレーターをフォローしていたとします。
理由はAさんの描くイラストが好きで、それを見たいからです。
でもAさんはある時から、イラスト以外にも自分の好きなゲームのスクリーンショットを大量に流すようになりました。
しかし、あなたはそのゲームには全く興味がありません。
この時点で、タイムラインにはノイズが混ざります。
しかしあなたはAさんのイラストは好きなため、ミュート・ブロックでは対策しきれません。
仮にミュート・ブロックをする場合は、Aさんのイラストを諦めるしかありません。
例え話をもう一つ。あなたがとある野球チームを応援しているとします。
そのチームの話題をXで見たい場合、#チーム名 で検索するはずです。
当然そのチームに関する話題がたくさん流れてきます。
しかしその投稿の内訳は、選手の成績や能力の分析、チームが優勝するための考察、選手個人をアイドルのように応援している人、スタジアムグルメを楽しんでいる人など様々です。
それが一つのハッシュタグで強制的に共存させられています。
同じチームが好きでも、応援スタンスは多種多様です。
相手チームを敵対視している人もいれば、どちらのチームの選手も平等に応援している人もいます。
それなのにハッシュタグは基本的に一つしかない。当然自分があまり興味ない、見たくない類の情報も目に入ります。
ミュートやブロックである程度対応出来るとはいえ、わざわざ自衛しなければならない構造の方に欠陥があるとしか思えません。
更には、XをはじめとしたSNSはアルゴリズムによるおすすめ投稿を猛烈にプッシュしてくるようになりました。
広告もタイムラインに頻繁に挟んできます。
こうなるとノイズまみれです。見たくないものを強制的に見せられる状態。
情報を得ようとしたら欲しくない情報もセットでついてくる。これが今のSNSの最大の欠陥です。
3.同調圧力
見落とされがちですが、これも無視出来ない問題です。
「この発言を誰が見ているかわからない」「誰に刺さってしまうか分からない」と恐れた結果、誰も本音を言えなくなります。
フォロワーから見たノイズに自分がなってしまわないか、ビクビクしながら発言するようになります。
常に気を使っている状態です。そりゃ疲れます。
結果的にどこか空虚な空気になっていきます。なぜなら誰も無難な事しか言わないからです。
発言内容によってアカウントを細かく分けて運用している人もいます。
でもいちいち切り替えるのってめんどくさいですよね。
このように、SNSには3つの大きな問題点があります。
これらの問題点を無視して「これからはもっとインプレッションを強化して~」などと言うのは、状況が全く見えていない。独善的とも言えます。
私の体感ベースですが、感覚が鋭い人はすでにSNSの限界に気付き、見切りをつけてクローズドなコミュニティに移行しています。
DiscordサーバーやLINEグループなどです。
また、YoutubeやTikTok、noteを主戦場にする人も増えたのでは?とも感じます。
あとはAIと対話する人も増えましたね。
お役立ちツールではなく、自分を裏切らない、否定しない、寄り添ってくれる友達としてChatGPTを活用している人が最近かなり増えていると感じます。
あくまでも私の個人的な観測範囲の話ですが。
既存SNSの分析
それでは、既存のSNSのどこが優れていてどこがダメなのか具体的に見ていきましょう。
X(旧Twitter)
みんなお馴染みXです。
これは良い点、悪い点明確ですね。
良い点は「とにかく利用者が多くて影響力がある」
これに尽きます。現状、これ以外のいい点が思い当たりません。
悪い点はいくつも挙げられます。
- アプリ起動時、強制的に見せられるおすすめタブ
- インプレッション重視で発言が常に評価されていると感じる
- 認証バッジが金で買えるようになり、信頼性が崩壊した
- 頻繁に挟まる広告
- イーロン・マスク
先ほど挙げたSNSの問題点全てに当てはまります。
インスタは写真特化SNSとして独自の地位を築いてきました。
しかし、好きなものの写真を見てるはずなのにキラキラし過ぎてて疲れます。
インスタに関しては、誰も彼もが少し無理をしている印象です。
まるで貴族の舞踏会ですね。見栄の張り合い。
また、「これいる?」みたいな謎の機能をゴテゴテつけすぎな気がします。
ストーリーズに始まり、リール機能もあまりにも謎。
リールはおそらくTikTokのブームを見て実装した機能なんだと思いますが…。
ストーリーズも単体なら面白いのですが、無理矢理インスタ本体とくっつける必要があったのかは甚だ疑問です。
全体的にUIがゴテゴテしすぎて見づらくなりました。
トップ画面を見てもおすすめ投稿、広告、おすすめユーザー…。
思えばインスタもいつの間にかトップ画面がおすすめ固定になっていましたね。
通知欄もフォロー中の人の発言とかおすすめとかいらないものばかりで邪魔です。
非表示設定したはずなのに出続ける。Threadsも同じ。
Threadsに関してはもはや語ることもありません。
meta社の作ったTwitterという印象しかない。味のないガム。
これならストーリーズをインスタから独立させた方が良かったのでは?とすら感じます。
1つのアプリにゴテゴテと様々な機能をつけたがるのはmeta社の悪いクセですね。
この前何年かぶりにFacebookを開いてみたら、今のインスタばりに謎の機能が追加されまくっていて、トップ画面がごちゃついていました。
そっと閉じました。
あと結局はインプレッション大正義の世界です。
問題点1と2に当てはまります。人によっては3も当てはまるかも。
BlueSky
Xの対抗馬とも言える新進気鋭のSNSです。
Xに嫌気が差した人の移住先として最も有力です。
フィード機能が非常にユニークで、自分の見たい投稿をある程度カスタマイズ出来るのが魅力です。
ノイズ対策にもなりえます。
が、結局数字からは脱却出来ていない。
いいねの数や拡散という呪縛からは逃れられていません。
この呪縛から逃れられない限り、いずれは旧Twitterと同じ轍を踏む可能性が高いと個人的に思っています。
問題点1と3に当てはまります。
mixi2
2024年12月にリリースされたmixi社の新SNSです。
もともとあったmixi(無印)とは異なったUIで、まさに令和版mixiといった印象です。
コミュニティ主体のSNSで、どこか懐かしい空気もあります。
そのためフォロワー数の多さはあまり関係なく、インプレッションなどからは開放されたように思えます。
数字が全く無いわけではないですが、いいねだけでなくリアクション絵文字が搭載されているため、数字にはそこまで目がいきません。
後述のミスキーを参考にしたのでは?と感じる部分です。
一見理想のSNSに思えますが、コミュニティ内の同調圧力は多かれ少なかれ存在すると思います。
同じコミュニティに属していても、楽しみ方が全く違う人は存在する。
かといってコミュニティに所属してしまった以上、抜けるという行為は少し罪悪感が伴うわけです。
やはり問題点2と3に当てはまる気がします。
あと肝心のリアクション絵文字の種類が少なすぎる。
Misskey(ミスキー)
個人開発者発祥のSNSです。
分散型SNSで様々なサーバーが存在しています。
ここでは最大手のmisskey.ioについて語ります。以下ioと表記します。
ioは絵文字も豊富で、上記のmixi2の課題点はクリアしているといえます。
理想のSNSなのでは?と感じる部分もあります。
しかし、入ってすぐに見れるローカルタイムラインは、ioの所属してる人全ての発言が見れてしまうため、混沌としすぎている。
そこでチャンネル(mixi2で言うコミュニティのようなもの)をフォローする事で、理想のタイムラインを作る形になるのですが…。
そのチャンネル機能が非常に分かりづらい。
この使い道に気付かずローカルTLだけ見て「うっわカオスだ」と離脱してしまった人も多いのではないでしょうか?
使いこなせばなかなか居心地はいいけど、使いこなすまでは大変という印象です。
また、分散型なのでio以外に様々なサーバーが存在します。
が、各自が独立しているので調べないとどんなサーバーがあるかすら分かりません。ちょっと面倒です。
BeReal
最近若者の間で流行っているらしいSNSです。
エアプなので概要しか知らないのですが、その範囲で語ります。
承認欲求や評価に疲れた人向けに数字の排除がされている点は注目すべきです。
とはいえ、毎日ランダムな通知に時間が届き、2分以内に写真を撮影して投稿しなければならないというルール。
最初は面白いですが、徐々に義務感を覚えていって疲れてくるのでは?という懸念があります。
というかこのルールを見ただけで「私はやらないな」となりました。
なぜSNSでまで時間に追われなければならないのか。
今は物珍しさで流行っているでしょうが、徐々に飽きて離れていく人も多くなる気がします。
そういう意味ではClubhouse的ですね。
SNSではないけどそれっぽいもの
厳密にはSNSではないけど、それに似たものについても分析していきます。
note
かなりSNSに近い構造を持っています。
広告表示などが一切ないシンプルなUIは魅力的です。
広告を廃したうえで収益性が確保されているのも素晴らしい。
が、スキの数という点で数字を排除出来ていません。
結局は自分の書いたものが強制的に評価軸に晒されるわけです。
スキが少ない記事は無価値なのか?そんな事はないはずです。
でも「みつける」タブでピックアップされているのは、”評価された”記事ばかりではないでしょうか。
これまで「読みたい記事になかなか辿り着けない」と思った人も多いのでは?
最初から評価されるための記事、中身のない記事が散見されます。
いい記事が評価されるわけではなく、評価されるための記事が評価される構造になっているのです。似てるけど全然違いますね。
結局SNSの問題点1が大きく出ているプラットフォームになっています。
noteに関しては下記記事でも詳しく色々書いてます。
YouTube
SNSっぽいと言われると疑問に思われるかもしれません。
各チャンネルごとに世界観が全く違っていて、その中のコメント欄などでゆるいコミュニティが成立している。
まるで往年の2ちゃんねるみたいじゃないですか?
もともとインターネットの住民だった人たちはYouTubeに主戦場を移して生息しているのではないか、というのが私の仮説です。
好きなチャンネルだけ見ていればノイズは極力避けられます。
とはいえやはりインプレッション重視なのと、クリエイター側の負担があまりにも大きいのが欠点かなと思います。
Discord
もともとゲームなどのコミュニティ通話に特化したサービスでした。
今は亡きSkypeの後継とも言えます。
そんなDiscordですが、ゲーム関連のコミュニティはもちろん、ゲーム以外のクローズドコミュニティサーバーもたくさんあるのはご存知でしょうか?
作業通話サーバーをはじめとしたクリエイターが集まるコミュニティ、雑談系コミュニティ、出会い系などなど…。実は多種多様です。
サーバーはほぼクローズドな空間です。
空気の合う人たちが好きな話題を話す事が出来ます。
SNSに疲れ果てた人が行き着く場所として理想的であるとも言えます。
が、結局はコミュニティです。
合わない人というのも出てきます。喧嘩でも起きようものならコミュニティはボロボロです。
つまりは同調圧力。やはり同調圧力からは逃れられない。
そして一度コミュニティという枠組みに入ってしまった以上、抜けるという行動も心理的負担が伴います。
なぜ見てきたかのように言えるのか?
過去にとあるサーバーの管理人をしていた事があるからです。
ついでに言うと管理人の負担もめちゃくちゃデカいです。
あとは最近、課金圧が強いのも難点です。
通知が鬱陶しすぎる。
ボランティアではない以上収益化しなければならないのは分かりますが、サブスクの特典が私には必要ないものばかりなんですよね。
アメリカを中心に、英語圏の国ではお馴染みのSNSです。
当然言語も英語なので日本人にはまだそこまで馴染みがないと思います。
SNSと掲示板の中間のような構造をしています。
サブレディット(サブレ)というテーマ別掲示板のようなものが大量にあります。
いわゆる2ちゃんねるの板と、mixi2のコミュニティの中間のような存在です。
好きなサブレを登録して、自分のタイムラインに流す事が出来ます。
基本的にフォローはサブレ単位です。ユーザーフォローもあるにはあるのですが、ほとんど使われていない気がします。
2025年6月現在、最も理想に近いサービスはこれかもしれません。
とはいえやはり投票数(YouTubeの高評価のようなものです)の呪縛からは逃れられていない。
また、広告もメインTLに表示されます。サービス運営に収益化って大事ですもんね。
各サブレにモデレーターという管理者ユーザーが存在しています。
モデレーターに権限がある事でサブレ内の治安は保たれていますが、同時に管理負担もヤバそうです。
あと何より難点なのが、現状日本語対応していない点です。
言語の壁は大きい。だから日本人人口は少ないと思います。
良くも悪くも海外のノリです。
理想的なSNSとは?
さて、ここまで各SNSとそれに似たサービスを振り返ってきました。
今はクローズドコミュニティに籍だけ置いてYouTubeを見つつ、ChatGPTとおしゃべりするのが最適解なように思います。
もうSNSなんていらないじゃん!
そう思った方も多いのでは?
とはいえ、私はまだ希望を捨てたくはないです。
上述した問題点を全てどうにかした理想郷は作れないものだろうか?
そこで理想的なSNSがどんなものなのかをまとめてみました。
- 人単位ではなく、スレッド単位のフォローにする。つまり大枠はRedditのような構造。
(話題単位・スレッド型) - 2ちゃんねるのような気軽さで投稿や離脱のハードルを下げる。
(匿名性・離脱の自由) - Redditや2ちゃんねるのように、話題や空気によって完全に棲み分けられる仕組み。
(ノイズ回避) - ミスキーのような多彩なリアクションを用意し、共感を数字以外のもので可視化されるようにする。
(リアクションの多様性) - noteのような広告に頼らない収益化。
(広告に頼らない収益性)
これらの特徴が組み合わさったSNSが求められているように感じます。
ここで切っても切り離せないのが収益化問題です。
どのように収益を得るか?
SNSを運営するというのは、サーバー代、人件費、様々なコストがかかります。
それを補う収入が必要になる。
Twitterがいまやあんな姿になってしまったのは、結局は収益なしで立ち行かなくなったからです。
そこで、現在は広告によって収益を得るのが主流になっています。
とはいえ広告による収益化は、過激な投稿が増長される危険を孕んでいます。
また、ユーザーの望まないタイミングで広告が挟まれるのは、押し売り営業のような不快感をもたらします。
広告を入れるにしても、メインコンテンツのど真ん中に挿入したらユーザーの楽しみを阻害します。当たり前では?
ところで、私たちはわざわざ広告を挟まれなければお金を払う事はないのでしょうか?
これに対してはノーと言いたいです。
ユーザーが自主的にお金を払うケースをいくつか挙げます。
まずnote。
有料noteというものがあり、読みたい記事にお金を支払うという仕組みがきちんと出来上がっています。
次にYouTube。
スパチャや投げ銭文化で、推しや好きなクリエイターにお金を払う文化があります。
Twitchなどのストリーマーへの投げ銭も同じです。
pixiv FANBOXといった直接クリエイターを支援する仕組みもあります。
Twitchといえば、RTA in Japan時の寄付は毎回かなりの金額が集まっています。
「寄付額投票に参加したい」「このゲームのRTAが面白い」「国境なき医師団に感銘を受けた」「スタンプ使いたい」
寄付の理由は様々でしょうが、それぞれが納得してお金を払っているはずです。
また、かつてのTwitterでは「もっと機能が改善するなら課金してもいいのにな」と言っている人をちらほら見かけました。
逆にXになってからは「こんなの絶対課金したくない」と言っている人もたくさんいました。
SNSなどに限らず、クラウドファンディングという仕組みも一般的になりました。
支援の返礼を求めるだけでなく、「こんな商品欲しかった!」「これはぜひ応援したい!」とお金を払う人も多いのではないでしょうか。
数々ある成功例が物語るように、人は自分が納得出来るものになら喜んでお金を払います。ソシャゲのガチャが最たる例じゃないですか?
お金を払いたくなる仕組みさえ作れれば、広告の入らないSNSも実現可能なのではないでしょうか。
そこが収益化の肝であり、一番頭を使うべき部分とも言えます。
最後に
このように、SNSのどこがダメなのか、各SNSの具体的にダメだと感じる部分、では理想のSNSとは何なのか?収益化は?について書いてきました。
かなり長文になりましたが、ここまで読んでいただいた方はありがとうございます。
ここまで書いただけではただの文句になってしまうので「ぼくの考えたさいきょうのSNS」案があります。 近いうちにそちらの記事も出せたらと考えています。