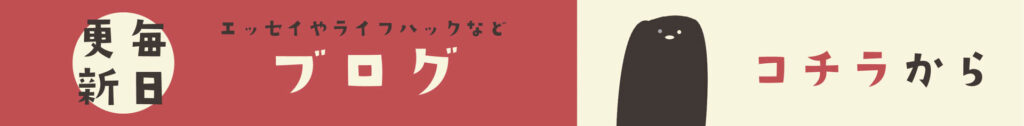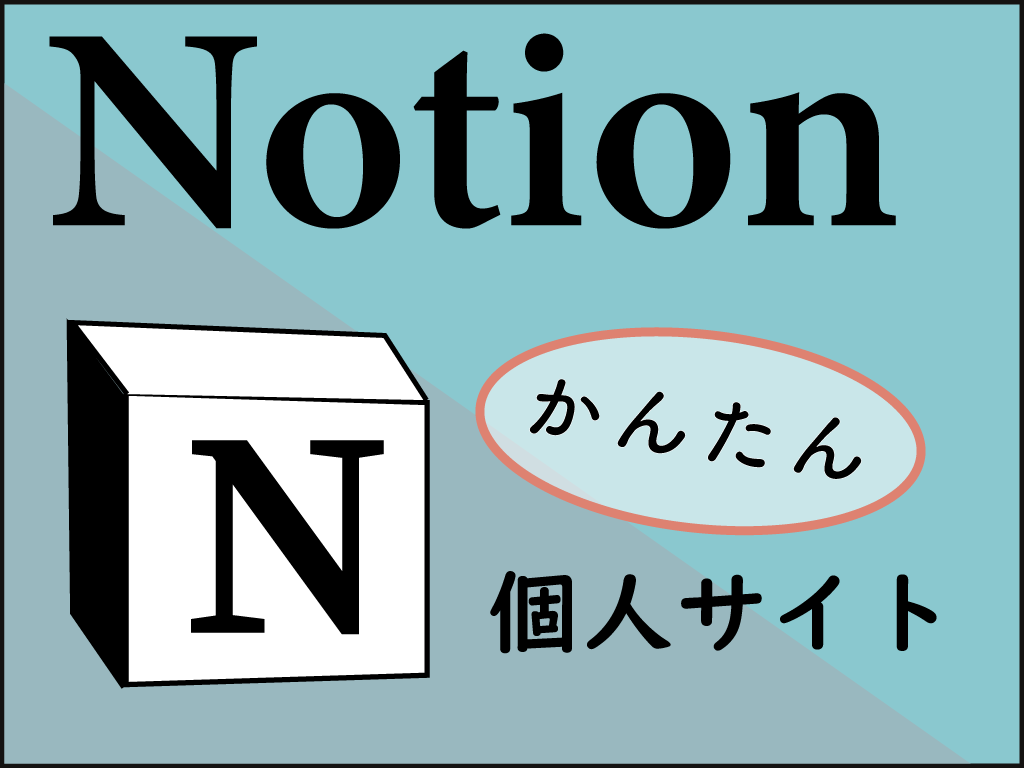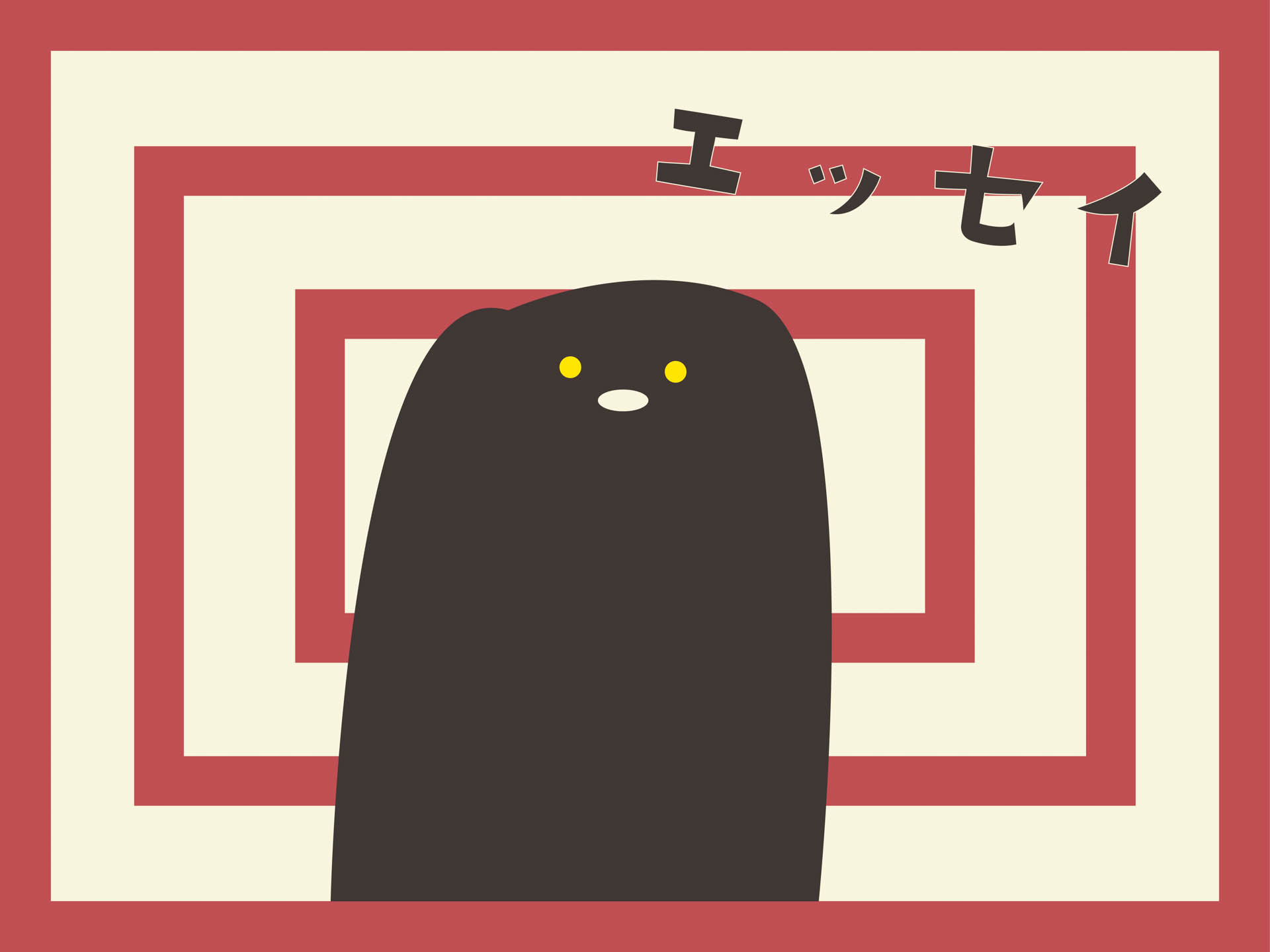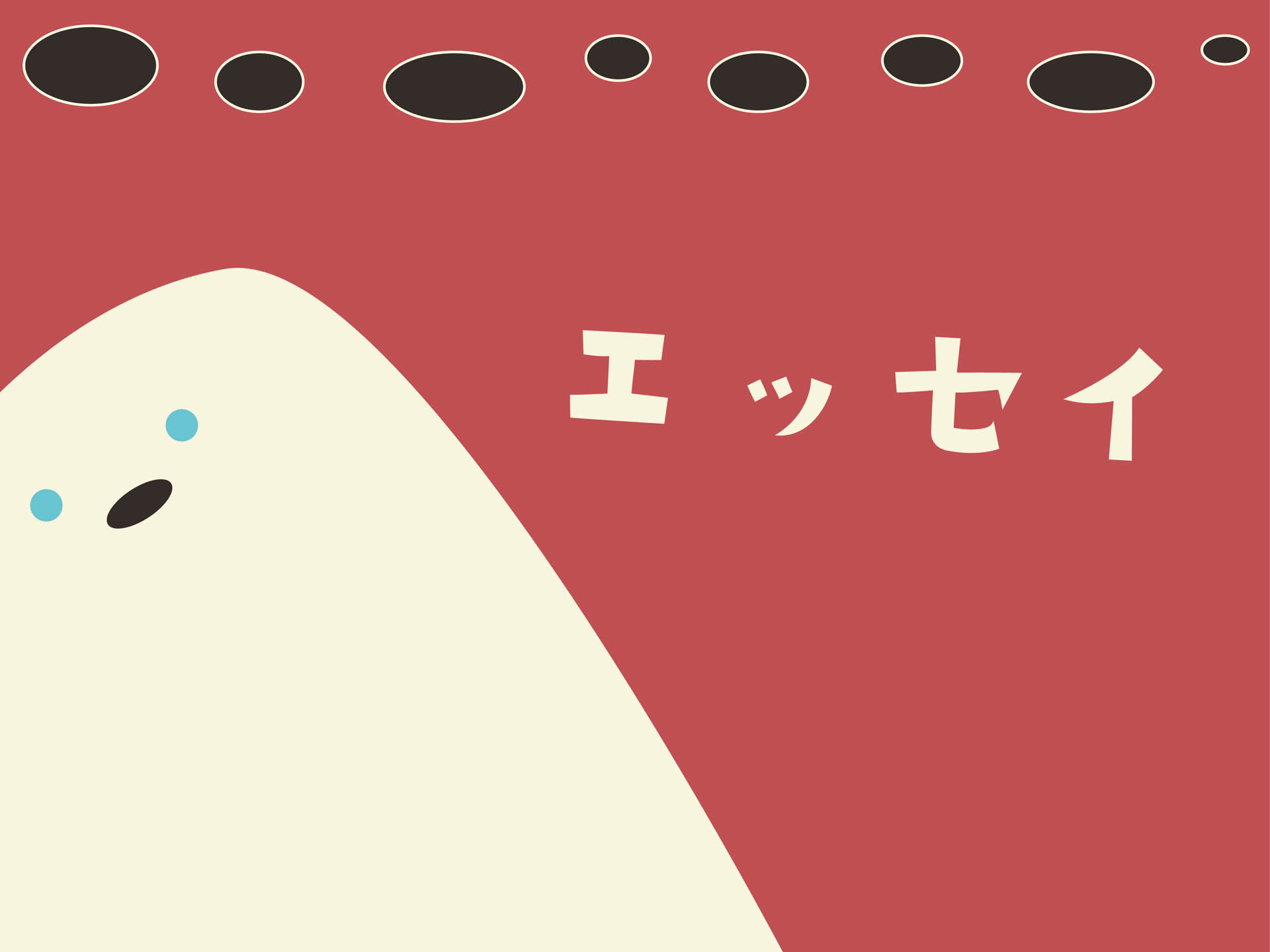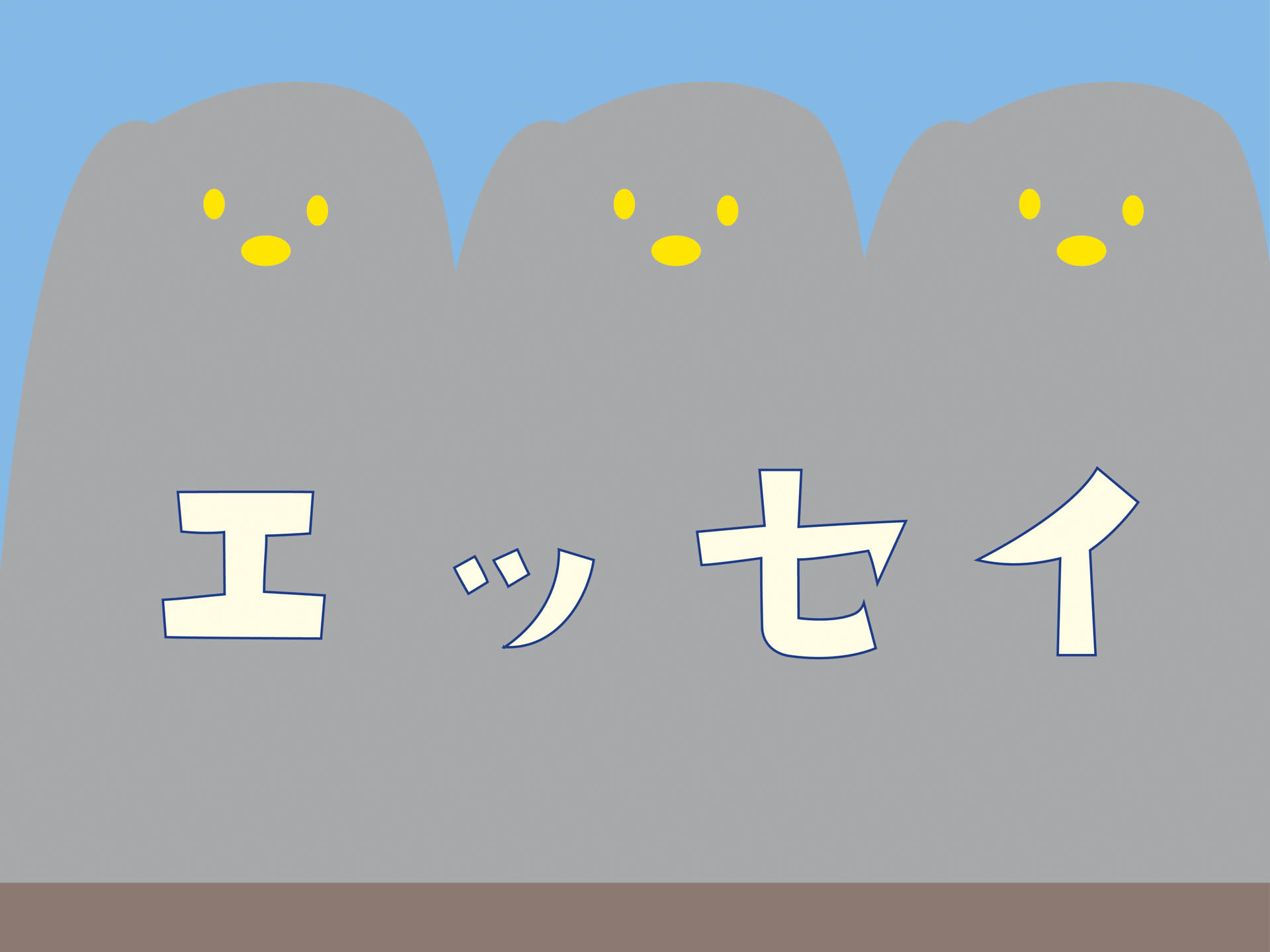幸福の正体とは?
途上国や昔の日本の状況を見る。
大抵は世襲制だ。
農家の子供はそのまま家を継ぐだろうし、基本は親の跡を継ぐ。
生まれた時から役割が決められていて、そこから逸脱する事はほぼ無かった。
とはいえ、現代の価値観からしたらこれは不幸と判別されるだろう。
はたして本当にそうだろうか?
少なくとも彼らは、自分が何者なのか思い悩む事は無かったのではないだろうか。
与えられた役割をこなして、次の世代に託していく。
シンプルだ。
「自分が何者なのか?何をなすべきなのか?」といちいち悩む必要はない。
自己が揺らぐ事はない。
パン屋の子供は大人になってパン屋の跡を継ぎ、親になり、次の世代に託し、死んでいく。
それ以外の可能性は「無いな」と一蹴される。
与えられた役割をただこなせば全てが上手くいくはずだった。
だがこの一見完璧な計画が上手くいかないのは、旧ソ連の社会主義政策を見ても明らかだろう。
敷かれたレールの上だけ走って満足出来る人間は少ない。
可能性を見出してしまった人間に社会主義の理屈は通用しない。
だからパン屋の息子として生まれた少年がロックスターを志したりする。
さて、可能性が開かれたのが現在だ。
ここで一つの疑問が浮かぶ。
我々は本当に幸福になったのだろうか?
おびただしい数の可能性が目の前に浮かぶ。
あれをやる自分、これをやらない自分…
様々な可能性が浮かびながらも、結局はその中の1つだけしか選ぶ事は出来ない。
その選択には常に後悔と不安がつきまとう。
パン屋の息子として生まれても「あなたの可能性は無限大だから好きなことをやりなさい」と言われる。
そして数多の選択肢を提示され、頭を抱える。
パン屋を継ぐべきか、継がないか、都市部で生活するか、地元に残るか、A社に就職するか、B社にするか、はたまた…。
この膨大な選択肢に頭を悩ませる事になる。
恵まれているという事は、膨大な選択肢に常に頭を悩ませる事と同義だ。
それは果たして本当に幸福と言えるのだろうか?
結局のところ、多くの人が自分の可能性を限定する事でやり過ごしている気がする。
「自分にはこれしか出来ないから」
まあその「何をやるか」を自分で選び取れるようになったのは大きな進歩なのかもしれない。
パン屋の息子がギター1本持って「俺にはこれしかないから」と歌い続ける。
だが結局は様々な迷いが生じるだろう。
「やっぱりパン屋を継いでおいた方が良かったのではないか」
「本当にこの道で合っているのか?」
「自分に才能なんてないのでは?」
油断すると迷いの森に誘われる。
迷いの森で散々彷徨った結果、やはりパン屋を継ぐことになるのか、ロックスターを突き詰めるのか。別の道か。
それは誰にも分からない。その時になるまで本人にすら分からないだろう。
迷った結果見出した答えは、おそらく最初よりは揺るぎないものになっているに違いない。
結局、この文章の終着点が見えない。
私はこの文章で何が言いたいのだろう。
Geminiに「結論がわからない」と聞いてみた。
1. 現代における「限定」の再定義
無限の可能性が提示された結果、かえって迷いが生じる現代において、自ら可能性を「限定」することが、新たな幸福への道ではないかと締めくくる方向です。
2. 「選択の苦悩」そのものが現代の幸福の条件であるという視点
選択肢が多いことによる苦悩や不安は、現代に生きる私たちの宿命であり、その苦悩を乗り越えることこそが、現代における「幸福」の条件であると主張する方向です。
3. 個人の物語としての幸福の追求
幸福の形は時代によって変わるものであり、現代における幸福は、外部の基準ではなく、個人の内面に問いかけることで見つけられると結論付ける方向です。
Gemini
私の言っているのは2や3に近いんだろうが…
陳腐だ。
こいつが語るとなぜこんなに陳腐に見えるんだろう。
これが答えだと自信を持って提示してくるあたりだろうか。
所詮はただのAI。
寄り添って一緒に悩む事などしない。
「一般的に正解だと思われている」ような事を提示して「お役に立っているつもり」の陳腐な機械に過ぎない。
これなら素直に「私にはよくわかりません」と言っていた方がよっぽどマシだろう。
私が生成AIを心底嫌いなのはこれに尽きる。
これに気付いてから自分の心理を壁打ちする機会はめっきり減った。
今のままのこいつに人間の代わりは無理だ。
結局何が言いたかったんだっけか。
恵まれた環境じゃない人たちでも(命の危険が脅かされていなければだが)思いの外幸福に見えるし、人が幸福なのか否かは「恵まれているか」では判断出来ないということなのかもしれない。
選択肢の多さは幸福に直結する可能性も高いが、終わりのない迷路に迷い込む危険性も孕んでいる。
表向き金持ちでも、心が貧しい人間。
反対に、表向き貧乏でも心が豊かな人間。
こういう事なのかもな。
でも無理に結論づける必要はないのだろう。
思考のプロセスをそのまま記すのがいいのかもしれないな。
そもそもこんな事を考え出した理由は、途上国とかどこかの部族の人たちの映像を見たら、思いの外幸せそうな顔をしていたからだったような気もする。